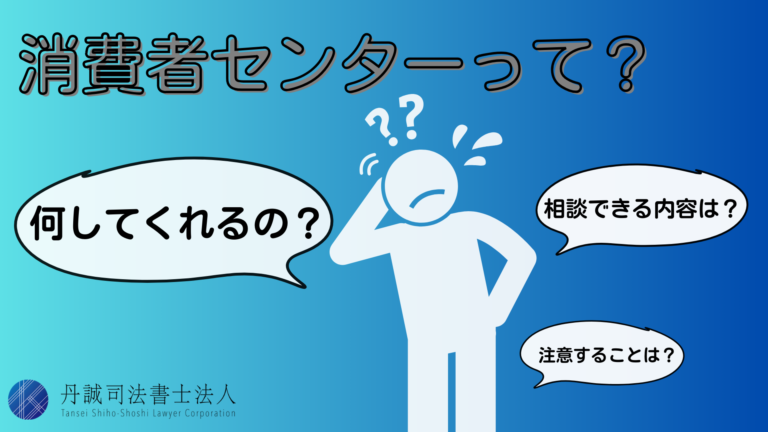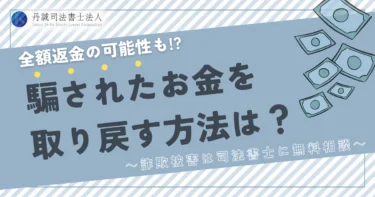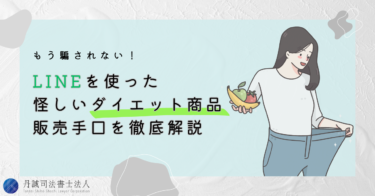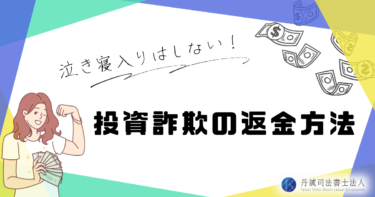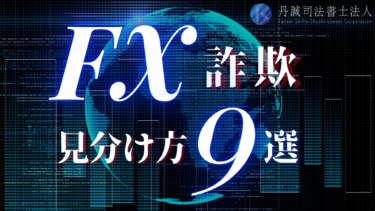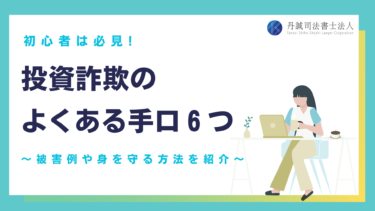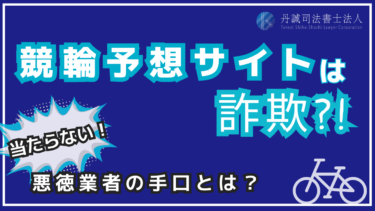「消費者センターは、具体的に何をしてくれる?」
「相談してもトラブルが解決しなかった場合は、どうしたらいい?」
消費者センターの利用に関して、上記のような不安を抱えていませんか。本記事では、消費者センターでできることや相談方法、解決しないときの対処法を紹介します。
\心当たりがある人はすぐ相談!/
消費者センター(消費生活センター)とは?

消費者センターとは、商品の購入やサービスの契約など「消費生活全般」に関する相談を受け、トラブル解決に向けたアドバイスを行う機関です。
消費者センターは地方自治体が独自に設置しているため、名称は「消費生活センター」「生活センター」「消費生活支援センター」など、地域によって異なります。
消費者庁「令和5年度 地方消費者行政の現況調査」によると消費者センターは全国に857か所あり(令和5年4月1日現在)、専門の相談員がさまざまな相談に対応しています。
国民生活センターとの違い
独立行政法人国民生活センターは国が運営しているのに対し、消費者センターは地方公共団体が運営している点が大きな違いです。国民生活センターは消費者問題に関する中核的な機関として、全国の消費生活センターと連携し問題に取り組んでいます。
消費者にとってメインの相談窓口は、市町村に設置されている消費者センターです。ただし、消費者センターが閉所している土日祝日や、消費者センターに電話がつながらない場合は、国民生活センターへの直接相談が可能です。
消費者センターでできること

消費者センターに相談した際、対応してもらえる内容について解説します。
トラブル解決に向けた助言・情報提供
消費者センターに相談することで、事業者との交渉の方法や具体的な解決策に関する助言・情報提供が受けられます。
商品・サービスの購入や契約などにおけるトラブルだけでなく、架空請求・悪徳商法による被害や多重債務などの相談にも対応しています。相談内容によって「専門家の支援が必要」と判断された場合は、適切な機関を紹介してくれることもあります。
電話で相談した場合は通話料がかかりますが、相談自体は何度でも無料のため、経済的な負担を抑えられるのがメリットです。
交渉の手伝い
消費者と事業者の交渉力に格差がある場合、相談員が事業者との間に入って交渉の手伝い(あっせん)をするケースもあります。
ただし、消費者センターによるあっせんは法的な指導権限や強制力を伴わず、相談員が代理人になることもできません。消費者センターの「あっせん」とは、あくまでも消費者と事業者との間に入り、公的な立場から話し合いの手伝いをするものです。
また、窓口の担当者によって対応に差があり、交渉の手伝いをするかどうかも消費者センター側の判断になります。
消費者センターに寄せられる相談内容5つ

2023年度には、約89万件もの相談が全国の消費者センターへ寄せられました。では、実際の相談はどのような内容なのでしょうか。よくある相談事例を紹介します。
通信販売での定期購入
消費者センターには通販関連の相談が多く寄せられますが、なかでも多いのが定期購入に関するトラブルです(2023年度の相談件数は約8万件)。
<実際の相談例>
その1.インターネット広告を見て化粧品をお試しで注文したら、解約の連絡をしない限り届き続ける「定期購入」だった。すぐに解約手続きをしたが間に合わず、2回目の商品が届いた。
その2.SNS広告を通じて購入したサプリメントが、4回の受け取りが条件の定期購入であった。「1回限り」であることを確認したうえで購入したため、納得できない。
「いつでも解約可能」と記載されていても、実際は電話がつながらなかったり、Web上の解約手続きがうまく進められなかったりするケースもあります。
多重債務
多重債務とは、すでにある借金を返済するために、ほかの貸金業者から借り入れる行為を繰り返し、返済が困難になる状態を指します。多重債務に関する相談も、年々増加しています(2023年度の相談件数は約2万件)。
<実際の相談例>
その1.複数のカードローンで借金し、返済が困難になってしまった。どうすればいいのか。
その2.リボ払いの設定になっていることを知らないまま、クレジットカードを使っていた。返済額が膨らみ、困っている。
2010年に施行された改正貸金業法によって、過剰な貸し付けの抑制や金利の適正化などの対策がとられているものの、依然として多くの相談が寄せられています。
架空請求
利用した覚えのない請求が届く架空請求も横行しています。まったく根拠のない請求にもかかわらず「支払わないと自宅へ出向く」「訴訟・差し押さえをする」などと脅す悪徳業者も存在します(2023年度の相談件数は約1.6万件)。
<実際の相談例>
その1.身に覚えのない電力会社から「未払いがある」というメールが届いたが、無視してもいいのか。
その2.電話で「有料サイトの料金が未納」と言われ、個人情報を伝えてしまった。悪用されないか心配だ。
悪徳業者はメールやSMS、ハガキなどさまざまな手段で架空請求を行いますが、身に覚えがない場合は決して連絡しないようにしましょう。
賃貸住宅の原状回復トラブル
賃貸の退去時に「賃借人と賃貸人、どちらが原状回復の費用を負担するか」を巡り、トラブルに発展するケースも多いです(2023年度の相談件数は約1.3万件)。
<実際の相談例>
その1.入居時からついていたフローリングの傷まで原状回復費用に含まれており、納得できない。
その2.アパートの退去時にクロスの張替えなど高額な原状回復費用を請求されたが、全額支払う必要があるのか。
原状回復に関する借主・貸主の費用分担は、契約内容や賃貸住宅の状況などによって異なるため、トラブルに発展しやすい傾向があります。
訪問販売によるリフォーム工事・点検商法
訪問販売を通じて不要なリフォームを勧める詐欺的行為や、「工事をしないと危険」と騙して商品やサービスを契約させる「点検商法」に関する相談も多数寄せられています(2023年度の相談件数はリフォーム工事約1.1万件、点検商法約1.2万件)。
<実際の相談例>
その1.突然自宅に訪れた業者に「屋根が傷んでおり、落ちてくる危険性がある」と不安を煽られ、高額な工事の契約をした。作業後に確認したらずさんな作業だった。
その2.業者に勧められ通気口フィルターを契約したが、事前に説明された金額と請求内容が異なっていたためクーリング・オフしたい。
消費者センターへの相談方法

消費者センターへ相談する方法は、電話・直接訪問・メールの3つがあります。
消費者センターへ電話で連絡する
最寄りの消費者センターに電話をかければ、相談員とつながります。消費者センターの電話番号を知らない場合、消費者ホットライン(電話番号:188)に連絡すると、最寄りの消費者センターの窓口を案内してくれます。
土日・祝日で最寄りの消費者センターが開所していない場合は、国民生活センターに電話がつながります。
最寄りの消費者センターへ直接訪問する
近くの消費者センターへ訪問することで、対面での相談も可能です。地方自治体によっては予約が必要な場合もあるため、対面での相談を希望している場合は事前に問い合わせることをおすすめします。
メール・Webフォームから相談する
都道府県や市町村によっては、電子メールやWebの専用フォームでも相談を受け付けていることがあります。各自治体の消費生活相談窓口一覧は、下記のページから確認できます。
消費者庁「メール等でも相談を受け付けている各自治体の消費生活相談窓口について」
消費者センターを利用する際の注意点

消費者センターに相談する前に知っておきたい注意点を解説します。
個人間のトラブル・人間関係のトラブルなどは相談できない
消費者センターは消費生活に関する相談を受け付ける機関のため、以下のような内容には対応していません。
- 個人間のトラブル
- 人間関係のトラブル
- 労働問題
- 相続や家族関係のトラブル
消費者と事業者間の契約トラブル以外の相談をしたい場合、適切な相談窓口を案内してくれることもあります。
原則として相談者本人が連絡する必要がある
相談員がトラブル内容の詳細を正確に把握するために、原則として本人が電話しなければなりません。ただし、病気や認知症など、やむを得ない事情で本人が電話できない場合は、介護や見守りをしている方が代理で相談できます。
トラブルに至った経緯や状況をまとめておく
消費者センターに相談する前に、以下の資料をまとめておきましょう。
- トラブルに至った経緯のメモ
- 約款や契約書
- チラシやパンフレット
- 広告画面や注文画面のスクリーンショット
上記の資料が手元になくても相談可能ですが、問題解決のために必要な情報は細かく聞かれるため、あらかじめトラブル内容を整理しておくとスムーズです。
通話料は相談者の負担になる
消費者センター・国民生活センターへの相談は無料ですが、窓口につながった時点から通話料金が発生します。携帯電話会社の通話料定額サービスを契約していても、別途ナビダイヤル通話料がかかるため注意してください。
相談時は個人情報を伝える必要がある
消費者センターへ相談する際は、氏名や住所、電話番号、性別、年齢、職業を聞かれます。とはいえ相談員には守秘義務があるため、個人情報や相談内容が外部に漏れる心配は不要です。また、本人の同意なしに個人情報がほかの目的で利用されることもありません。
消費者センターで解決できないときの対処法

消費者センターに相談しても事業者とのトラブルが解決しない場合、以下の対処法を検討してみてください。
\すでにお金を払ってしまったら/
裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、公正中立な第三者が間に入り、話し合いを通じて問題の解決をはかる手続きです。手続きの方法には、以下のような種類があります。
- 裁判所が行うもの(民事調停・家事調停・裁判上の和解など)
- 行政機関が行うもの(国民生活センターの紛争解決委員会など)
- 民間事業者が行うもの(士業団体・業界団体・NPO法人など)
ADRは裁判を介さないため費用を抑えられ、各分野の知見を持った人が間に入ってくれる点がメリットです。
消費者団体訴訟制度を利用する
消費者団体訴訟制度とは、内閣総理大臣に認定された消費者団体が、消費者の代わりに事業者に対して訴訟を起こせる制度です。
裁判外紛争解決手続(ADR)の場合、相手が話し合いに応じないと解決に至りませんが、消費者団体訴訟制度は訴訟を起こせるため、トラブルが解決するケースも多いようです。
弁護士・司法書士に相談する
裁判外紛争解決手続(ADR)や消費者団体訴訟制度はコストが抑えながら問題解決を目指せるものの、公共的性質があるため迅速な個別対応は難しいのが現状です。
できるだけ早急にトラブルを解決したい場合は、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。弁護士・司法書士に依頼すれば、相手と交渉する煩わしさから解放され、依頼者にとって有利に解決できるよう力を尽くしてくれます。
まとめ
消費者センターでは、事業者とのトラブル解決に向けた助言・情報提供のほか、相談員が間に入り交渉の手伝いをしてくれるケースもあります。ただし、担当者によって対応が異なるため、必ずしも希望の対応をしてもらえるわけではありません。早急な解決を目指す場合は、弁護士・司法書士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。丹誠司法書士法人では、消費者トラブルに関して豊富な実績をもつ司法書士が依頼者様に寄り添い、問題解決のお手伝いをします。
相談は無料ですので、一人で悩まずにぜひお話をお聞かせください。
なお以下の記事では、返金を目指して司法書士へ相談・依頼した場合の流れなどを解説しています。「いきなり依頼するのは勇気がいる…」という方は、以下の記事を参考に返金までの道のりをイメージしてください。
「騙されたお金を取り戻す方法は」 「実際に手元にお金が戻ってくるのはいつごろなの?」 などという疑問や不安な気持ちを抱いたことはありませんか? 丹誠司法書士法人ではどのように詐欺被害に関する無料相談から返金請求に関する手続[…]