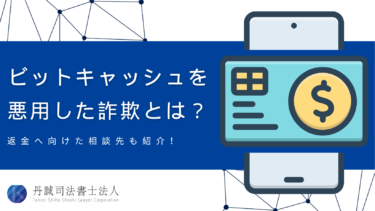最近では、小学生がスマホをもっている光景も珍しくありません。
小中学生を中心とした「子供たち」でも気軽に使えるうえ、防犯アイテムとしても有効なスマホですが、使い方を誤ると思わぬトラブルへと発展します。特に問題なのがゲームやアプリに関する「課金トラブル」です。国民生活センターには「親が知らないうちに、子供が勝手に課金をしていた」という相談があとを絶ちません。
本記事では、子供をもつすべての親御さんに知ってほしい課金トラブルについて、事例や防止方法、相談先などを解説します。
✓実際におきた課金トラブルの事例
✓子供が勝手に課金した場合は、返金される?
✓子供のスマホ課金への防止策5つ
子供が家でスマホゲームをしている時間の平均

1日のうち、子供がスマホを利用している時間の平均は、年々増加傾向にあります。子供にまつわる行政を担当する機関「こども家庭庁」が行った調査結果をもとに、子供たちのインターネット利用状況を解説します。同調査は、満10歳から満17歳の子供、計5,000人を対象に行ったものです。
5,000人のなかで「インターネットを利用する」と回答した人の平均利用時間は、約4時間57分。前年度と比べ、約16分増加していました。内訳は高校生が約6時間14分、中学生が約4時間42分、小学生(10歳以上)が約3時間46分でした。小学生が平均して4時間近くインターネットを利用しているというのは驚きです。
目的ごとの平均利用時間は、趣味・娯楽が多く、約2時間57分でした。課金が発生するゲーム・アプリの利用も多く含まれます。
スマホを保有している小中高生は、何にスマホを使っているのでしょう。先ほど解説したように、インターネットの利用目的に「趣味・娯楽」と答えた子供たちは数多くいます。
前述の調査では利用目的について、より詳細なアンケートを実施していました。利用目的に関するアンケート(※)によると、全体のうち約72%が「ゲームをする」と回答しました。小学生や中学生、高校生と年代を分けた結果でも、すべての年代で「ゲームをする」という回答は、66.5〜74%と高水準になっています。
※参考:こども家庭庁|令和5年度『青少年のインターネット利用環境実態調査』
子供の課金トラブルとして多いのが「オンラインゲーム」
子供が勝手に課金していたというトラブルが頻発しているのは「オンラインゲーム」です。ゲームでの課金は、スマホだけに留まりません。家庭用ゲーム機からもインターネットに接続でき、もちろん勝手に課金することも可能です。スマホの利用時間だけでなく、ゲーム機の管理にも注意を払ってください。
子供がクレジットカードを勝手に使ってしまう状況はさまざまです。たとえば、親のアカウントへログインしていたり、親がスマホを触っているときの手元を見てパスワードを覚えていたりです。「キャリア決済を使うと無料」と友達から教えられ、勝手に課金してしまったという事例もあります。
子供が「決済完了メール」を削除していたことで発覚が遅れ、気づいた時点ではすでに高額な料金が引き落とされていることも珍しくありません。
実際におきた課金トラブルの事例

ここまでの内容を踏まえて、実際の事例を紹介します。
上記の事例のように、決済完了メールを削除してしまう子供もおり、発見が遅れてしまうケースはたびたび目にします。
子供が勝手に課金した場合は、返金される?
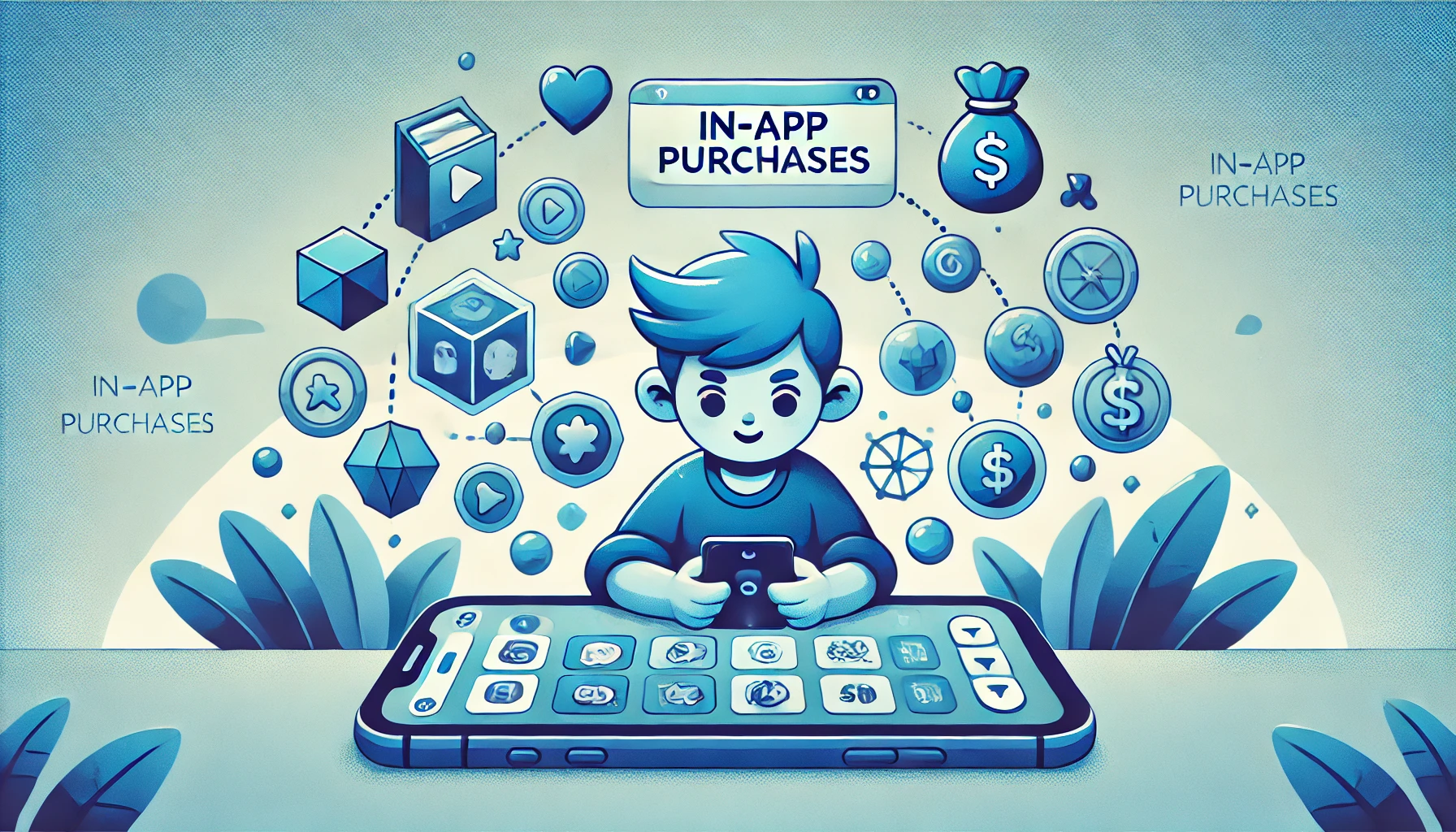
子供が勝手に課金をしていて、とんでもない金額を請求されたら、パニックになってしまうかもしれません。トラブルのときこそ落ち着いて、親子でよく話し合い、ルールを決めましょう。そのうえで、すでに支払っているお金をどうするのか、冷静に相談先を考えてください。
問い合わせ先として、真っ先に思い浮かぶのが、ゲーム会社やアプリ運営会社といった「課金先の企業」です。しかし相手から見れば、親の名義で勝手に課金している以上、本当に「子供が勝手にやったことなのか」判断できません。そのため、購入の取り消し・返金に応じてもらえない可能性があります。運営元が応じてくれない場合は、消費者センターや弁護士・司法書士事務所へ相談してみましょう。
消費者センター
身近な相談先としては「消費者センター(消費者ホットライン188)」がよいでしょう。子供が勝手に課金した場合、原則として民法で「未成年者取消権」が認められているため、契約を取り消せます。しかし相手によっては、返金に応じてくれないかもしれません。
しかし消費者センターの場合、相手へ直接的に返金を命じることはできません。あくまでもお互いの間に立ち、やりとりをスムーズにしてくれるだけです。
弁護士・司法書士
消費者センターでも返金されなかった場合は「弁護士」や「司法書士」を頼ってみましょう。弁護士や司法書士には交渉権があるため、相手企業(ゲームやアプリの運営元)に直接交渉してくれます。
子供が行ったゲーム課金を取り消す際、難しいポイントと考えられるのが「子供が使ったことの証明」です。クレジットカードの名義やキャリア決済の請求先は親です。親自身が決済した履歴も含まれているなかで、ゲームの課金だけ子供がやったと主張するのは、難しいかもしれません。そのことを踏まえて、司法書士や弁護士に相談してみましょう。
子供のスマホ課金への防止策5つ

子供が勝手に課金してしまうのを防ぐ方法は、いくつかあります。ただし注意してほしいポイントは、多くの防止策は継続して行う必要がある点です。
- ルールを決めたら、子供が守っているか確認する
- クレジット決済の履歴は、日頃から確認する
- 子供にお金の知識を身につけさせる
日頃から、上記を徹底しておきましょう。
1.オンラインゲームのルールを設ける
トラブルなく、子供にスマホを与えるためには、一定のルールを設けてください。多くのご家庭で、子供のスマホ購入時にルールを定めているでしょう。たとえば「◯時までしか使わない、」「使う時間は1日◯時間にする」などです。
上記にくわえて、オンラインゲームに関するルールも決めておきましょう。課金を許すか許さないかはもちろんのこと、許す場合は、月々の金額(お小遣いの範囲内)についても子供と話し合ってください。課金をするときは、両親どちらかに確認するといった、条件付きの許可もよいかもしれません。
2.クレジットカードの管理・利用制限
子供とルールを決めるだけでなく、親の方もクレジットカードの管理を徹底すべきです。親の知らない間に、子供が勝手に課金を繰り返していた事例として「クレジット決済の履歴が残っていたこと」が、原因であるケースが多く見られます。面倒に感じても、クレジット情報が残ったままのスマホを子供に渡さないように徹底してください。
クレジットカードの保有者(名義人)には「クレジット情報をしっかりと管理する義務」があります。クレジット情報を削除せず子供に端末を渡した場合は、請求元が「本当に子供が使ったのか」判断できないだけでなく、管理義務も怠っていると判断されてしまいます。
3.お金に関する教育を徹底する
お金の稼ぎ方や使い方などお金に関する教育は、学校ではなかなかできません。子供であっても家族の一員であるため、子供扱いせずにご家庭の「経済状況」を説明してあげるのも方法の1つです。
キャッシュレス化が進み、子供に正しい金銭感覚が身についていないことも原因かもしれません。ゲーム内をはじめとしたバーチャルな空間では、どうしても「お金を使った」という意識が生まれにくくなります。お年玉やお小遣いなどを、あえて現金で渡すことも有効です。
4.頭ごなしに叱らない
頭ごなしに叱っても、根本の解決にはなりません。親も子供も感情的になって、話の内容が身につきません。頭ごなしに叱られると子供は、なぜいけないのかを理解できず「次からはバレないようにしよう」という思考に陥ってしまいます。隠す方法ばかり上手になってしまい、根本の解決にはなりません。
大声で怒鳴って叱るのではなく、親子で話し合うことが重要です。「なぜ課金をしてはいけないのか」「今後どうすればよいのか」をしっかりと話し合いましょう。
特に「今後はどうするか」というルールは、必ず親子で決めてください。スマホの使い方だけでなく家庭内における、あらゆる「親子のルール」を決める際は、子供にも参加してもらいましょう。一方的に「〇〇しなさい」と命令するのは、効果的ではありません。
5.ペアレンタルコントロールを利用する
ペアレンタルコントロールとは、子供がもつ端末の利用方法を、親が管理できる機能です。利用時間や閲覧できるサイト、アプリのダウンロードに至るまでさまざま制限を設けられます。親が保有している端末から制限をかけられるため、手軽に使える機能です。
いくらルールを決めていても「バレないだろう」「少しぐらいなら…」「〇〇(友達)もああ言っていたし」と誘惑に負けてしまうのが、子供という生き物です。子供がある程度の年齢になれば、親が細部まで管理できません。成長とともに親の目は届きにくくなるため、便利な機能はどんどん活用しましょう。子供が勝手に課金することを防ぐには、動画でも解説しているため、ぜひ参考にしてください。
@tansei_legaloffice 子供が勝手にゲームで課金!?防止策を紹介します! #課金 #課金トラブル #子供課金 #詐欺相談 #副業 ♬ オリジナル楽曲 – 丹誠司法書士法人
まとめ
子供がゲームで勝手に課金をしていた場合、ある日突然、とんでもない金額の書かれた請求書が届くかもしれません。子供は課金してしまったことを、必死で隠そうします。結果として、決済にまつわるメールを削除してしまい、発覚が遅れることも珍しくありません。
「なんとかして、取引を無効にしたい」と考えている人は、司法書士・弁護士への相談がおすすめです。丹誠司法書士法人では、無料相談を実施しています。お困りの方は、ぜひお問い合せください。