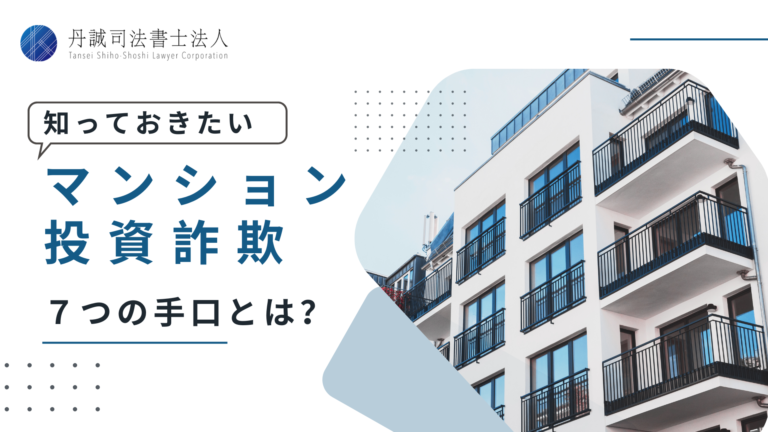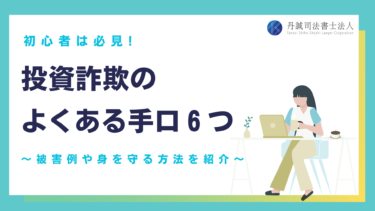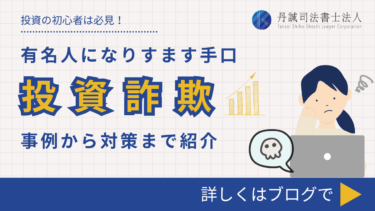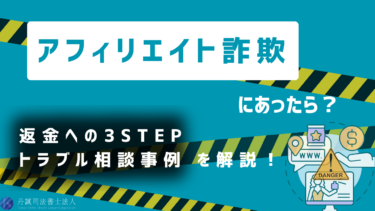マンション投資は資産形成の手段として人気ですが、詐欺まがいの悪徳業者による被害も多発しています。
マンション投資詐欺の手口は巧妙化しており、投資経験が少ない方はターゲットにされやすいため注意が必要です。
本記事では、マンション投資詐欺によくある7つの手口を紹介します。
悪徳業者に騙されないための対策法もあわせてお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
- マンション投資詐欺とはなにか
- マンション投資詐欺によくある手口
- 詐欺被害にあわないための対策法
- 被害にあった場合の相談先
マンション投資詐欺とは

マンション投資詐欺とは、投資用マンションの購入に関連した詐欺的行為のことです。
詐欺まがいの悪徳業者は、契約時に虚偽の情報を提供する・実在しない物件を購入させるなどの手口で、投資家から不当に金銭を騙し取ろうとします。
国民生活センターによると、2018年度に全国の消費生活センターなどへ寄せられた投資用マンションの相談件数は1,350件に上ります。
特に20代からの相談が多く、投資経験の浅い若年層が狙われやすい傾向があります。
詐欺まがいの悪徳業者は「年金・生命保険代わりになります」とメリットを強調したり、「今だけ特別価格です」と購入を急かしたりすることで、冷静な判断力を失わせようとします。
しかし、場合によっては多額の負担が発生するリスクもあるため、このような営業トークを鵜呑みにするのは危険です。
参考:国民生活センター|20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!-マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません-
投資詐欺は、投資用マンションを購入させるだけでなく、ほかにもさまざまな手口があります。
以下の記事では、投資詐欺全般の手口を解説しているため、あわせて参考にしてください。
投資は、自己資金を使って利益を得るものです。将来的な資産を作る手段として、投資を始める方が増えています。その一方で、投資家を狙った詐欺被害が増加傾向にあります。 特に初心者は、詐欺的行為のターゲットになりやすいです。そこで今回は、投資[…]
マンション投資詐欺によくある7つの手口

マンション投資詐欺によくある手口を知ったうえで対策すれば、被害にあう可能性を下げられます。
ここでは、マンション投資詐欺の代表的な手口を7つ紹介します。
1.サブリース詐欺
サブリースとは、不動産会社が物件を借り上げ、空室が発生した場合もオーナーに一定の賃料が保証される契約形態です。
一見すると空室リスクゼロで安定した収入が得られるように思えますが、「市場の変動に応じた賃料の見直し条項」などが契約書に含まれることが多く、実際は状況に応じて家賃を引き下げられることが多いため注意が必要です。
サブリース契約を巡っては、契約時に「空室時も毎月必ず〇万円の収入があります」などと説明しながら、家賃の減額や家賃保証契約の解除を強要される詐欺的行為が発生しています。
「家賃を永久保証します」といった営業トークを鵜呑みにせず、契約内容を十分に理解することが大切です。
2.満室偽装詐欺(架空賃貸詐欺)
満室偽装詐欺(架空賃貸詐欺)とは、実際は空室があるにもかかわらず満室であるかのように見せかけ、相場よりも高値で物件を売りつける手口です。
サクラを入居させて満室を装ったり、空室にカーテンをして入居者がいるように見せかけたりすることで、高い利回りが期待できると誤認させます。
満室偽装詐欺に騙された場合、物件を購入した途端に退去が相次ぎ、想定していた家賃収入が得られない可能性があります。
満室偽装詐欺の被害にあわないためには、契約前にレントロール(収益物件の賃貸状況をまとめた一覧表)を取り寄せ、直近で不自然な入居者が増えていないか確認しましょう。
ただしレントロールが改ざんされているケースもあるため、抜き打ちで現地調査を行い、入居状況の真偽を確かめる方法も有効です。
3.手付金詐欺
手付金とは、不動産の売買契約時に「契約が成立した」という意味合いで買主が売主に対して支払う金銭です。
詐欺まがいの業者は「手付金をいただければ物件を押さえておきます」「優良物件のため早く押さえたほうがいいですよ」などと支払いを強く促してきます。
しかし、手付金を支払ったあとで業者から「引き渡しができなくなった」などと一方的に契約を破棄され、お金を騙し取られる事例が報告されています。
このような場合、業者と連絡が取れなくなり、物件が手に入らず手付金も返還されないという被害に繋がります。
手付金詐欺に騙されないためには、業者の信頼性をよく確認することが重要です。
なお、手付金の相場は売買価格の5~10%が一般的です。あまりにも高額な手付金の支払いを要求された場合は詐欺的行為の可能性があるため、警戒しましょう。
4.二重譲渡詐欺
二重譲渡詐欺とは、売買済みの物件を第三者に再度販売し、代金を騙し取る手口です。
不動産は購入した順番にかかわらず、先に登記した人が所有権をもちます。
そのため二重譲渡詐欺の被害にあうと、後から登記しようとした人は手付金や代金を支払っていても物件が手に入りません。
二重譲渡詐欺を回避するためには、購入前に登記の内容を確認することが重要です。できれば、あらかじめ司法書士に登記情報を確認してもらうことをおすすめします。
また、契約後はすぐに所有権移転登記を行いましょう。
5.不正融資詐欺
不正融資詐欺とは、不動産業者や仲介業者が投資家の源泉徴収票や課税証明書などを改ざんして金融機関に申告し、本来は受けられない金額の融資を引き出す手口です。
投資家は自分の収入・資産に見合わないローンを背負わされ、返済不能に陥るリスクがあります。
改ざんが発覚すると金融機関から一括返済を求められる、投資家自身も文書偽造の罪に問われる可能性があります。
詐欺まがいの不動産業者は、投資家に無断で審査資料を改ざんする可能性が考えられます。
金融機関に審査資料を提出する際は、不動産業者・金融業者とともに投資家自身も立ち合い、書類の内容を自分の目で確認しましょう。
6.デート商法詐欺
デート商法詐欺とは、恋愛感情を利用して投資用マンションや商品を購入させる手口です。
マッチングアプリやSNSなどで出会い、親密になったところで投資を強く勧め、マンションを購入させるのがよくあるパターンです。
多くの場合、相場よりも高額な金額で売りつけられ、クーリング・オフ制度の期間を過ぎる頃に音信不通になるケースも少なくありません。
「相手に嫌われたくない」という思いから断り切れず、投資用マンションを購入してしまう方もいますが、出会ったばかりの相手から投資話を持ち掛けられた場合は詐欺を疑い慎重に行動しましょう。
7.海外不動産投資詐欺
実在しない海外のマンションや、極めて価値の低い物件を高額で売りつけられる「海外不動産投資詐欺」の被害も発生しています。
海外の物件は現地調査が難しく、契約手続きに外国語が用いられるため、騙されてしまうリスクが高いです。
海外物件を購入する際は、現地の不動産市場に詳しく、信用できる不動産業者に依頼することが重要です。可能な限り、購入前に現地調査することをおすすめします。
マンション投資詐欺の被害にあわないための対策法

悪徳業者にお金を騙し取られないためには、マンション投資詐欺のリスクを理解したうえで信用できる業者を見極めることが重要です。
ここでは、マンション投資詐欺にあうリスクを回避するための具体的な対策法を5つ紹介します。
不動産投資に関する知識をつけておく
不動産投資に関する知識が乏しいと悪徳業者を見抜きにくく、被害にあうリスクが上がります。
「友達の紹介だから」と契約内容をよく理解せず、営業担当者に勧められるまま投資用マンションを購入してしまい、損害が発生してしまうケースも少なくありません。
不動産投資に関する書籍やWebサイト、セミナー、不動産投資家のブログ、SNSなどで知識をつけてから物件選びや契約に進むことが重要です。
不動産投資の仕組みや物件の選び方、利回り計算の方法などの基礎知識はもちろん、税制・法制や金融の経済動向などの関連情報も一通り学んでおくことをおすすめします。
国土交通省の宅建業者検索システムで確認する
宅地建物取引業の免許を受けずに不動産の仲介などを行うことは、法律上禁止されています。
そのため、無免許で営業している不動産業者は詐欺まがいの行為をする悪徳業者の可能性が高いです。
国土交通省のサイトでは、宅地建物取引業(宅建業免許)を保有している会社のデータベースが公開されています。
「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で業者名を入力するだけで免許証番号や代表者名、所在地などが簡単にわかります。
免許証番号は「(04)第〇〇号」のように記載され、括弧内の数字は免許の更新回数を表します。
数字が大きいほど運営実績が長く、業者の信用度を判断するひとつの指標になります。
ただし、詐欺まがいの業者が実在する宅建業者を無断で名乗っている可能性もあるため、手付金を支払う前に不動産会社へ訪問してみることをおすすめします。
提示された販売価格が適正か確認する
不動産の適正価格を把握していないと、相場よりも高額でマンションを売りつけられる可能性があります。
国土交通省が提供する不動産情報ライブラリや、国土交通大臣指定の不動産流通機構が運営する「レインズマーケットインフォメーション」では、過去の成約価格(実際に売れた価格)が公開されています。
購入を検討しているマンションの類似物件がいくらで売れたか確認することで、おおよその相場がわかります。
不動産業者が提示してきた価格が類似物件と比べてあまりにも高額であれば、警戒しましょう。
マンション投資のリスクに関する説明があるか確認する
マンション投資には、リスクがつきものです。
たとえば空室や家賃の滞納により想定していた家賃収入が得られなかったり、老朽化に伴い不動産価値が下落したりする可能性があります。
また、金利の上昇や自然災害による建物の損害などのリスクも考えられます。
これらのリスクに一切触れず、おいしい話ばかりを持ち出して投資家の判断を鈍らせようとする不動産会社は悪徳業者の可能性があるため、契約を勧められても慎重に検討しましょう。
強引に勧誘された場合は警戒する
強引に契約締結を迫り、顧客に検討の余地を与えないのも詐欺まがいの悪徳業者によくある手口です。
以下のように、執拗に勧誘してくる・契約を急かしてくる業者には注意してください。
- 断っても電話を切ってくれない・しつこく電話してくる
- こちらの都合を一切考えず「とりあえず会いましょう」と強引に迫る
- 飲食店などで長時間拘束され、強引に契約を急かしてくる
契約を断ろうとすると「わざわざ時間を作って説明したのに手間をかけさせられた」「社会人として失礼だ」と不動産業者が怒り出し、不本意なまま物件を購入させられるケースも発生しています。
高圧的な態度を取られても、契約の意思がなければ毅然とした態度で断りましょう。
マンション投資詐欺の被害にあった場合の相談先

万が一マンション投資詐欺の被害にあってしまった場合は、早めに第三者へ相談し、適切に対処することが重要です。
ここでは、マンション投資詐欺の相談ができる窓口を紹介します。
\心当たりがある人はすぐ相談!/
消費生活センター
全国の市区町村に設置されている消費生活センターでは、マンション投資詐欺を含む消費生活全般の相談を受け付けています。
詐欺まがいの悪徳業者と契約してしまっても、一定の条件を満たせばクーリング・オフできる可能性があります。
クーリング・オフできるかどうかの判断や書面の書き方、通知方法なども消費生活センターに相談可能です。
消費者ホットライン(電話番号:188)にかければ最寄りの窓口につながり、専門の相談員が対応してくれます。
ただし、消費生活センターで対応できるのは問題解決に向けた助言のみであるため、契約解除や返金請求は自分で行う必要があります。
免許行政庁
マンション投資詐欺の被害にあった際は、免許行政庁への相談も有効です。
免許行政庁とは、不動産業者に対する監督処分を行う機関です。
詐欺的行為の証拠や被害の詳細を免許行政庁に通達することで、悪徳な不動産業者に対して営業停止や免許取消などの行政処分が下される可能性があります。
担当の免許行政庁や連絡先は、国土交通省のサイトで確認できます。
ただし、免許行政庁が監督するのは宅地建物取引業免許を持つ業者に限られ、無免許の業者に対しては警察への通報などの間接的な措置に留まります。
宅地建物取引業保証協会
詐欺まがいの不動産業者が宅建業者であれば、宅地建物取引業保証協会への相談も可能です。
宅地建物取引業保証協会とは、宅建業者とのトラブル対応や、問題が解決しない場合の補償業務を行う団体で、全国の宅建業者の約80%が加入しています。
行政機関ではないため、悪徳な宅建業者に対して法的措置は取れませんが、必要に応じて国土交通省などへ告発してくれる可能性があります。
苦情の解決業務窓口一覧は、宅地建物取引業保証協会のサイトで確認できます。
司法書士・弁護士
不動産投資詐欺に精通している司法書士・弁護士に相談することで、騙し取られたお金を回収できる可能性があります。
詐欺まがいの業者の手口は非常に巧妙なため、不動産の知識がない個人が返金交渉しても取り合ってもらえない可能性が高いです。
しかし、司法書士・弁護士を代理人に立てることで、被害金を取り戻せる可能性が上がります。
無料相談を実施している司法書士・弁護士事務所も多いため、ぜひ利用してみてください。
まとめ
マンション投資を含め、リスクのない投資は存在しません。
相場より高額な販売価格を提示してくる・メリットばかりを強調する・強引に勧誘してくる会社は悪徳業者の可能性があるため、警戒が必要です。
契約前に不動産投資に関する知識を身につけ、不動産業者の信頼性をよく見極めましょう。
万が一、被害にあってしまった場合や疑わしい場合は、当事務所へご相談ください。詐欺か否かの判断や返金へ向けたアドバイスなどを行います。