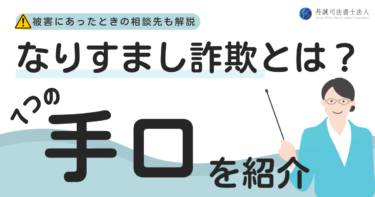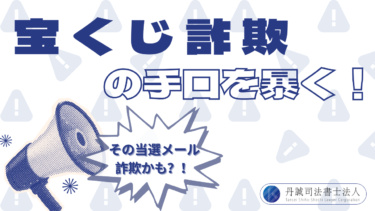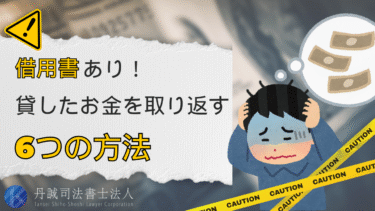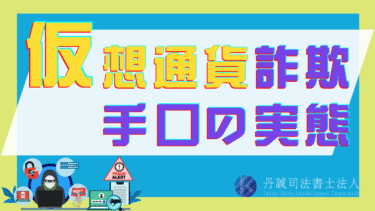「なりすまし詐欺の被害にあわないための対策方法を知っておきたい」「二度と同じ被害にあわないように予防法を知りたい」などのお悩みはありませんか。
なりすまし詐欺は手口が巧妙なため、騙されてしまう人が多いです。「自分が被害にあうはずがない」と自信がある人ほど被害にあってしまう恐れがあります。
そこで本記事では、なりすまし詐欺の特徴や概要、よくある事例を紹介します。
注意すべきポイントを押さえることで対策が立てられるだけでなく、悪徳業者からの誘引を防ぐ予防策も知ることができます。
✓なりすまし詐欺の特徴や見分け方
✓実際の被害事例
✓そもそも被害を避けるための予防策
なりすまし詐欺とは?

なりすまし詐欺の定義と種類を紹介します。
なりすまし詐欺は特殊詐欺の一種ですが、さまざまな手口で多くの人が被害にあっているのが現状です。
昔から存在している詐欺で、SNSが普及した現代ではさらに被害が拡大しています。
理解を深めなければ、被害にあってしまうかもしれません。
なりすまし詐欺の概要
なりすまし詐欺とは、全く関係のない第三者が公共団体や企業、著名人などを装って不正にクレジットカードの暗証番号や金銭、個人情報などをだまし取る詐欺のことです。
なりすましに利用されやすい人物や団体は以下のとおりです。
- 銀行
- 宅配業者
- 携帯電話会社
- 有名な芸能人や投資家
- 公共機関(役所、警察、裁判所)
- 弁護士
相手は「あなたの個人情報が悪用されていないかを確認するため」「あの有名人も参加している信頼できる投資情報」などと言葉巧みに話しかけてくるので、騙されないように注意しましょう。
なりすまし詐欺の手口
なりすまし詐欺はさまざまな手口で行われますが、大きく分けると3種類ほどに分類されます。
手口がわかれば、もし自分のもとに詐欺師が近づいてきても見抜くことができるでしょう。ここでは、なりすまし詐欺の手口を3つ解説します。
なお、より多くの手口を知っておきたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
インターネットが普及した現代において、サイバー犯罪はますます巧妙化し、私たちの生活を脅かしています。 近年、深刻な問題となっている「なりすまし」もその1つです。 なりすましとは、実在する個人や企業になりすます行為のことです。また[…]
メールやSMSで行われるもの
メールやSMSを使ったなりすまし詐欺は多くの人が被害を受けている手口の一つです。
受信を希望しているかどうかに関わらず、詐欺師は金融機関や公的機関、誰もが知っている有名企業などを装ってメッセージを送りつけます。
この手口は、特定企業のロゴやデザインを利用して本物のように見せかけていることが特徴的です。
たとえば「銀行のシステムに不正アクセスが発生したので、アカウントの認証が必要です」「未払いの料金が発生しています」といった内容で個人情報の入力やリンク先へのアクセスを求めるメッセージが届きます。
アクセスすると偽のウェブサイトに誘導され、そこで情報を入力すると口座情報や個人情報が盗まれてしまう恐れがあります。
電話で行われるもの
「オレオレ詐欺」を筆頭に、電話でのなりすまし詐欺も依然として横行しています。
詐欺師は、身内のほかにも企業のカスタマーサポート担当者や警察官、金融機関の職員などを装って電話で個人情報や金融情報を聞き出そうとします。この手口では、すぐに対応しなければならないと、被害者を焦らせることが特徴的です。
たとえば「口座が不正に利用されているので、至急対応が必要です」「警察が関与している事件にあなたの情報が含まれています」といった緊急性のある内容で被害者を信じ込ませます。
被害者は焦って指示に従ってしまい、個人情報やパスワードなどを口頭で伝えてしまうケースが増えています。
SNSやメッセージアプリによるもの
近年ではSNSやメッセージアプリを利用した詐欺も急増しており、手口は年々巧妙化しています。
たとえば友人や知人になりすまし、「情報を拡散されたくなければ金銭を支払え」「急な用事でお金が必要」などといった理由で送金を求めるメッセージを送る手口もあります。
特定の有名人や企業の公式アカウントを模倣し、フォロワーに向けて「抽選に当たりました」「特別な割引が受けられます」といったメッセージを送信して、個人情報やクレジットカード情報を入力させようとするケースもあるでしょう。
なりすまし詐欺だと見抜くための対策5選

手口が狡猾なため、大勢の方が被害にあってしまいかねないのがなりすまし詐欺の恐ろしさです。
しかし、なりすまし詐欺には特徴があるため、ポイントさえわかれば見抜くことができます。
ここでは被害を生み出さないために見分けるポイントを解説します。ぜひ参考にしてください。
対策1.メールアドレス・文章を確認
メールアドレスやメールの文章を確認しましょう。
たとえば、なりすまし詐欺メールでは送信元メールアドレスの一部が「amazoe」になっているなど、公式名称と綴りが異なるものが見受けられます。
また、文章を読んでみると違和感があったり、文字化けをしていたり、明らかに異常だとわかるものが多いです。
たとえば、「あなたはそれを〇月×日までに〇万円支払う必要がある」のように不自然な日本語で書かれているなどです。
このように、メールアドレスや内容をみると簡単に見分けられるでしょう。
対策2.公的機関が暗証番号を聞いてくることはない
役所や警察がクレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を直接聞いてきたり、預かったりすることはまずありえません。
「あなたのキャッシュカードが偽造され、使われている」「マイナンバーカードの保険証利用登録のために口座番号や暗証番号、所得や資産の情報を教えてほしい」と聞かれたら、詐欺業者かもしれないので、注意してください。
個人情報が含まれているものは、家族や親戚などの親しい人にもむやみに口外しないようにしましょう。
対策3.一度検索してみる
「役所の職員を名乗る人から、指定の銀行口座にATMでお金を振り込むように言われた。還付金を受け取るために必要らしいけど…。」
「ATMで操作ができる」「還付金がもらえる」「暗証番号を教えてほしい」などのフレーズが出てきたら要注意です。詐欺の可能性が高いので、一度インターネットで検索してみてください。
似たような事例が多数報告されているので「似たようなパターンだからなりすまし詐欺かもしれない」と気づけるかもしれません。
おかしいと思ったら、相手が名乗った組織名と内容で一度検索してみましょう。
対策4.よくある事例と共通点がないかを確認
なりすまし詐欺は手口が巧妙ですが、ある程度騙し文句のパターンが決まっていることが多いです。
以下がよくあるパターンです。
- 暗証番号や口座番号を聞かれる
- 添付ファイルやリンクをクリックするように催促される
- キャッシュカードやクレジットカードの提出を求められる
- 個人情報の登録、または伝えるように指示される
- 家族構成や所得・資産額を聞かれる
これらを知っておくだけで、被害を被る前に対処できます。
対策5.不自然に急かしてくる・重要性の高さを強調している
役所の職員やとある企業の社員を名乗る人物から連絡を受けたとします。
もし必要以上に催促を受けたり重要性を強調されたりする場合は、なりすまし詐欺の可能性が高いです。
詐欺業者は「至急」「重要」「今すぐ確認」などの言葉で対象者を焦らせて正常な判断をできなくさせ、自分たちの指示に従わせるのが目的です。
高額なお金が請求されたり情報が漏洩していると聞くと、緊急性が高いと判断し慌ててしまうかもしれませんが落ち着いて冷静に対応してください。
なりすまし詐欺の被害事例を2つ紹介

代表的な手口が用いられた事例を2つ紹介します。
この事例を覚えておけば、似たような内容の連絡がきてもなりすまし詐欺だと見抜くことができるでしょう。
事例1.公的機関を装った訴訟請求(80代女性)
80代女性の事例
「民事訴訟管理センター」という公的機関を名乗るところから、料金の支払いが確認できないという旨の封書が届きました。
女性は全く心あたりがなかったものの、何か不手際があったのかもしれないと思い指定された連絡先に電話しました。
すると、今度は弁護士事務所の電話番号を伝えられ、弁護士から高額な料金の支払い命令を受けました。
事例2.被災者を装ったチェーンメール(T県)
T県で起きた事例
この事例は、K県で震度7を超える地震が起き、いまだに復旧の目処がたっていないというニュースが流れている最中に起きました。
ある日、T県に住むGさん宛に、とある団体から「K県の復旧にあたって募金活動をしています。指定の口座に振り込んでください」「被災地では物資が足りていませんが、あまり知られていません。このメールを転送して多くの人に届けてください」といったメールが届きました。
被災地の手助けになればと思い、Gさんは1,000円募金しメールを友人や家族に転送することにしました。
その後、その団体は架空の団体であることがわかり、Gさん自身も1,000円を騙し取られたうえに、友人や家族にも被害をもたらしてしまいました。
【安心】被害にあわないための予防策

なりすまし詐欺の被害にあわないために、効果的な予防策を紹介します。
ここまで、手口や対処法について解説しましたが、そもそも詐欺業者に接点をもたせないように工夫することが重要です。
ソーシャルエンジニアリング対策を行う
ソーシャルエンジニアリングとは、人間の心理や信頼関係を巧みに利用して、第三者が会社などの組織や個人から重大な情報を不当に引き出す行為をいいます。
詐欺業者が公的機関や大企業、有名人に偽装して不正にクレジットカードの暗証番号や金銭、個人情報などをだまし取るなりすまし詐欺もこれに該当するでしょう。
ソーシャルエンジニアリングの主な対策方法として、以下の内容があげられます。
- 迷惑メールフィルターを使用する
- セキュリティソフトを導入する
- 重要な書類やハガキはシュレッダーにかけて処分する
- 公共のWi-Fiを使用しない
- 大勢の人にみられやすい場所でID・パスワードを入力しない
- 席を外すときは、パソコンの画面をスリープ状態にする
狡猾なソーシャルエンジニアリング攻撃にも対応できるような工夫をしましょう。
ほかにも、お金をかけずにいますぐ実践できる方法を2つお伝えするので、ぜひ参考にしてください。
同じID・パスワードを使い回さない
ECサイトや金融機関、マイナンバーなどのID・パスワードはそれぞれ別のものに変えるようにしましょう。
万が一、自分の情報を企業が漏洩してしまったり自身の過失で外部に知られてしまった場合、その情報が悪用されるリスクがあります。
特に、ECサイトや金融機関のID・パスワードが全て同じにしていると、詐欺業者に情報が知られた際、利用している他のサイトでも不正利用される恐れがあります。
そのため、ID・パスワードは使い回さないでください。
複雑なID・パスワードを設定する
ID・パスワードを使い回さなくても、推測されやすい情報で設定するのは避けましょう。
シンプルな英数字の組み合わせなど、簡単なパスワードにしてしまうと、情報が漏洩していなくても第三者にアクセスされるリスクが高まります。
自分の生年月日や「1111」「1234」のようなID・パスワードは避けましょう。
ID・パスワードは複雑な組み合わせで設定するのに加え、顔や指紋認証などの生体認証、可能であればあなただけの質問と回答などもセッティングしておくのがおすすめです。
違和感をおぼえたら、まずは丹誠司法書士法人へ相談!
なりすまし詐欺は、第三者が有名企業や官公庁などの公的機関、有名人などに偽装し、不正に個人情報やクレジットカードの暗証番号、金銭などをだまし取る詐欺のことです。
巧妙な手口のため詐欺だとわからず、目の前の詐欺業者に対して自身の重要な情報を伝えてしまう方が多くいらっしゃいます。
しかし、なりすまし詐欺は明確な特徴があるため、よくある手口や事例を知っておけば被害を避けることができるでしょう。
「なりすまし詐欺の被害にあってしまったかもしれない」「被害にあわないための予防法をもっと知りたい」という方は、丹誠司法書士法人にご相談ください。
相談は無料です。なりすまし詐欺について少しでもお悩みがあればお気軽にお声かけください。