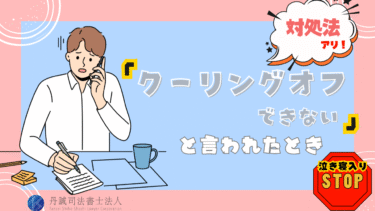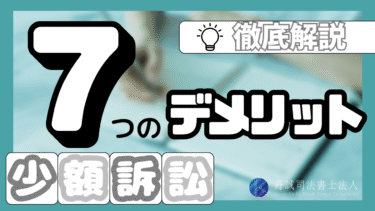SNSやインターネット上で「スマホひとつで月10万円稼げます」「誰でも不労所得を得られます」などと謳う広告を目にしたことはありませんか。
これは、ターゲットからお金を騙し取ることが目的の情報商材詐欺かもしれません。
被害にあわないためには、情報商材詐欺の典型的な手口を知っておく必要があります。
本記事では、情報商材詐欺の被害事例や見分け方、悪徳業者に騙されたときの対処法を紹介します。
- 情報商材詐欺とはなにか
- 情報商材詐欺の事例
- 詐欺まがいの情報商材の見分け方
- 情報商材詐欺に騙されたときの対処法
以下の記事では、情報商材詐欺の返金方法について詳しく解説しています。
「情報商材の詐欺被害にあったが、支払ったお金を取り戻せるのか」 「被害金の具体的な回収方法を知りたい」 こういった不安や疑問を感じていませんか。 情報商材詐欺に騙された場合、時間が経つほど返金の成功率が下がってしまうため、[…]
情報商材詐欺とは

情報商材詐欺とは「誰でも稼げる方法」などと称し、低品質の情報商材を高額で売りつける詐欺的行為のことです。
情報商材の内容は投資やアフィリエイト、副業、ギャンブル、異性の落とし方など多岐にわたります。
いずれにせよ「楽して稼ぎたい」「異性にモテたい」といった人々の欲望につけ込み、「この情報さえ入手すれば人生が変わるかもしれない」と期待を抱かせるのが情報商材詐欺の共通点です。
しかし実際は、調べれば無料で手に入るような情報しか書かれていない、指示どおりに行動しても成果が得られないなど、詐欺まがいの内容がほとんどです。
情報商材の特性上、購入するまで具体的な内容がわからないため、悪徳業者に騙されてしまう方が後を絶ちません。
特に若い世代の被害が多く、情報商材をきっかけに高額なコンサルティングやセミナー、オンラインサロンへ誘導されることもあります。
なかには消費者金融やローン会社の利用を促され、被害が数百万円に上るケースもあります。
情報商材詐欺の具体的な事例

情報商材詐欺では、SNSやWeb広告、求人サイトなどを入口にお金を騙し取られるケースが多発しています。
それでは、具体的にどのような手口で騙されるのでしょうか。
ここでは、情報商材詐欺の被害にあった方の事例を3つ紹介します。
【SNS経由】検索すれば無料で手に入る情報を数万円で買わされた事例
総務省が運営する「国民のためのサイバーセキュリティサイト」に掲載された被害事例です。
TさんはSNSで「簡単に儲けられる方法を教える」と謳う情報商材に興味を持ち、購入しました。
しかし、中身はSNSでフォロワーを増やすための方法やアフィリエイトの仕組みなど、インターネットで検索すれば無料で手に入るものばかりでした。
そのうえ「その情報商材を購入した後は、さらに高額な情報商材を買わないと儲けられない」という内容のメールも送られてきました。
ここで騙されたことに気づき返金を求めましたが、販売業者からの返答はなく、数万円の損失を被りました。
この事例のように、SNSを通じて「簡単に稼げる」という情報を発信してターゲットを引き寄せる手法が増えています。
SNSは匿名性が高く、相手がどこの誰なのか、どのような人物なのか正体がわかりません。
拾い画像などを使って虚偽の成功事例が作り上げられているケースも多く、それが真実かどうか確かめるのは困難です。
【Web広告経由】サポート付き65万円のプランを購入したが儲からなかった事例
続いて、2021年に消費生活センターに寄せられた20代女性の被害事例です。
Oさんは「アフィリエイトで簡単に儲かる」というWeb広告を見て、約3,000円のマニュアルを購入しました。
マニュアルには多くの有料プランが紹介されており、販売業者から電話で「有料プランに入らなければ儲からない。高額なプランほどさまざまなサポートが受けられる」と言われます。
Oさんは65万円のプランを契約し、業者の指示通りにブログを作りました。
しかし、毎日記事を書いても儲からず、業者と連絡も取れなくなりました。
最初に低額の情報商材を販売してターゲットの心理的ハードルを下げ、その後に高額な商材を売りつけるのが悪徳業者によくある手口です。
この事例のように「サポートが受けられる」と宣伝しながら、購入後に連絡が取れなくなるケースも少なくありません。
【求人サイト経由】「在宅で1日10万円確実に稼げる」と記載されていたが成果が出なかった事例
続いて、茅ヶ崎市のホームページに掲載されていた情報商材詐欺の事例を紹介します。
Fさんは、求人サイトで「在宅で1日10万円確実に稼げます。返金保証つき」「誰でも簡単にできる」と謳う広告を見つけ、信用して契約しました。
仕事に必要な情報商材を高額で購入させられましたが「すぐに元が取れる」と言われたため疑いませんでした。
しかし、業者の説明通りにやっても言われたような結果にはならず、到底稼げそうにありません。
解約・返金を申し出ましたが、拒否されてしまいました。
「最初に〇万円が必要だが、すぐに取り戻せる」「元が取れる」は、情報商材詐欺にありがちな決まり文句です。
初期投資のリスクを軽減できるように見せかけて安心感を与え、被害者を購入へと誘導するのが目的です。
しかし実際は稼げるどころか、多大な損失を被る可能性があります。
詐欺まがいの情報商材の見分け方9つ

ここでは、詐欺まがいの情報商材の特徴を9つ紹介します。
悪徳業者の見分け方を理解し、被害を未然に防ぎましょう。
1.SNS・Web広告・求人サイトなどから情報商材の購入を促される
多くの場合、詐欺まがいの情報商材はSNSやWeb広告、求人サイトなど、不特定多数のユーザーと接触できる場所で販売されます。
そのほか、YouTubeや副業サイトで「〇万円が〇億円になる投資法」「1日5分の作業で月30万円!」などと謳うケースもみられます。
また「おすすめの副業〇選」「人気の情報商材ランキング」と称するまとめサイトも販売業者が宣伝のために運営している可能性があるため、容易に信用すべきではありません。
2.「確実に月100万円稼げる」など誇大な表現を使っている
詐欺まがいの悪徳業者は「誰でも確実に100万円稼げるマニュアル」「FX必勝法」といった誇大広告でターゲットの購入意欲を高めようとします。
しかし、誰でも確実に・短時間で儲けられる方法は存在しません。
仮にそのような方法が存在するなら、見ず知らずの相手に教えるのではなく、独り占めするはずです。
ビジネスで成功するためには地道な努力が不可欠であり、投資やギャンブルにはリスクがつきものです。
誰でも簡単に高収入が得られる方法はないと認識し、非現実的な謳い文句に惑わされないようにしましょう。
3.販売者の情報が明記されていない
販売者の情報が明記されていない時点でほぼ詐欺まがいだと判断できるため、決してお金を支払わないようにしましょう。
情報商材をはじめとする通信販売では、販売会社の名称や代表者(責任者)の氏名、連絡先、住所などの明記が法的に義務付けられています。
詐欺まがいの悪徳業者が身元を明かさないのは、トラブル発生時に責任を逃れやすくするためです。
また、悪徳業者によっては社名や住所を捏造しているケースもあります。
販売会社の住所が記載されている場合はGoogleマップで検索し、事務所が実在するか確かめましょう。
4.特定商取引法に基づく表示がない
販売ページの一番下(フッター部分)など、わかりやすい場所に「特定商取引法に基づく表記」のリンクが設置されていない場合も要注意です。
特定商取引法では、運営者の情報だけでなく商品やサービスに関する情報の表示も義務づけられています。
情報商材の販売価格や支払いのタイミング、支払い方法、返品・契約解除の条件が明記されているか確認しましょう。
5.返金保証をアピールしている
情報商材詐欺では「万が一稼げなかった場合は全額返金します」「ノーリスクで購入できます」などと返金保証を謳っているケースも多く見られます。
これは「返金されるなら」と購入のハードルを下げるための罠に過ぎず、実際は何かと理由をつけて返金を拒否されます。
<返金保証の罠>
- 「すぐには成果が出ません。あと数か月教材の手順を試してみてください」と返金を引き延ばされた後、連絡が取れなくなる
- 「指示通りに行動していないので返金できません」と断られる
- 「指示通りに作業を行ったか確認できるものを提示してください」と無理な要求をされる
詐欺まがいの悪徳業者は、最初から返金に応じるつもりはありません。
「返金保証」の甘い言葉に誘惑されず、販売業者の信頼性を冷静に見極めましょう。
6.LINEやDMの個別メッセージに誘導される
「今なら友だち登録で無料マニュアルを3つプレゼント」などとLINEの登録を促されるのも、情報商材詐欺によくある手口です。
SNSでは、知らない相手から突然「稼ぎ方を教えます」といった勧誘のDM(ダイレクトメッセージ)が送られてくるケースもあります。
個別のやり取りで信頼関係を築き、ターゲットに安心感を抱かせるのが悪徳業者の狙いです。
「あなただけ特別に教えます」「本気で稼ぎたい人だけに紹介しています」と購入意欲を高めようとしてきますが、甘い誘い文句に騙されないでください。
7.電話やZoomのアポイントを設定される
LINEやDMでは情報商材の具体的な内容が明かされず、「詳しくは直接口頭で説明します」と電話やZoomのアポイントを設定されるケースも多く見られます。
悪徳業者は電話やZoomで営業トークを繰り広げ、「その場決済」「その場契約」を要求してくるのがよくある手口です。
電話やZoomはリアルタイムで会話が進むため冷静に考える時間がなく、業者に言われるがまま契約してしまう方も少なくありません。
電話やZoomで即決を要求されてもすぐに契約せず、いったん電話を切ってから慎重に検討しましょう。
8.消費者金融の利用を勧めてくる
詐欺まがいの悪徳業者から消費者金融の利用を勧められたり、紹介されたりするケースもあります。
よくあるのが、Anydesk(エニーデスク)という遠隔操作ツールを使って消費者金融から借金させられる手口です。
「借金ではなく分割払いです」「必ず儲かるので借金はすぐに返済できます」と嘘をつく悪徳業者も存在します。
良識のある会社なら、商材の購入のために消費者金融の利用を勧めることはありません。
「すぐに返済できるから大丈夫」「みんな借りている」と言われても、安易に消費者金融を利用しないようにしましょう。
9.ローン会社の利用を勧めてくる
情報商材や高額なサポートプランの代金を支払えないと伝えると、「提携しているローン会社があるからローンを組まないか」と勧めてくる悪徳業者も存在します。
「お金がないので…」という断り方をすると消費者金融やローン会社の利用を勧められる可能性があります。
断る場合は「やめます」「いりません」とはっきり伝えましょう。
少しでも違和感があればその場で契約せず、第三者に相談しましょう
\心当たりがある人はすぐ相談!/
情報商材詐欺に騙されたときの対処法

悪徳業者に大金を騙し取られるとパニックに陥ってしまう方も多いと思いますが、被害を拡大させないためには冷静な対処が重要です。
ここでは、情報商材詐欺に騙されたときの対処法を4つ紹介します。
すぐに支払いをやめて相手との連絡を絶つ
販売業者に対してメールや電話で返金を求めても、相手にされないことがほとんどです。
そればかりか、言葉巧みに言い包められ、さらなる支払いを要求されるリスクもあります。
騙されたと気づいたらすぐに支払いをやめ、業者との連絡を絶ちましょう。
自分一人で解決しようとせず、第三者に相談することが大切です。
できる限り多くの証拠を収集する
詐欺的行為の証拠が多ければ多いほど、返金請求や訴訟が成功する確率が高まります。
時間が経つと証拠を隠滅されるリスクが高まるため、騙されたと気づいたらすぐに証拠を収集しましょう。
<有効な証拠の例>
- 契約書
- 振込明細書・クレジットカード明細書
- 勧誘に使われたSNSの投稿内容のスクリーンショット
- 販売業者とのやり取り(メール・LINE・DM・電話の録音など)
- 情報商材に関する広告・販売サイトのURLやスクリーンショット
- 勧誘に使われたDM・メールマガジン・ステップメール
特に勧誘に使われたSNSアカウントや販売サイトなどはすぐに削除される可能性が高いため、すみやかにスクリーンショットに収めましょう。
証拠が十分に揃っていなくても返金交渉を進められるケースもあるため、まずは第三者に相談することをおすすめします。
消費生活センター・警察に相談する
全国に設置されている消費生活センターでは、情報商材詐欺に関する相談が可能です。
状況に応じたアドバイスが得られるほか、クーリング・オフが可能かどうかも判断してもらえます。
消費者ホットライン「電話番号:188」に電話すれば最寄りの消費生活センターにつながり、無料で相談に乗ってくれます(通話料は相談者負担)。
ただし、消費生活センターでは販売業者との交渉はしてもらえないため、クーリング・オフの申請を含めて自分で対応する必要があります。
また、警察相談専用電話「電話番号:#9110」でも情報商材詐欺の無料相談ができます(通話料は相談者負担)。
警察に相談すれば情報提供やアドバイスをしてもらえますが、民事不介入のため、必ずしも捜査してくれるわけではない点に注意が必要です。
司法書士・弁護士に相談する
騙されたお金を取り戻したいなら、司法書士や弁護士への相談がおすすめです。
情報商材詐欺に強い司法書士・弁護士に相談することで「返金できる可能性はどれくらいあるか」「どのような方法で返金請求するのがベストか」を判断してもらえます。
また、司法書士・弁護士なら業者の調査から相手方との交渉まで一任できるため、時間的・精神的な負担も大きく軽減します。
\無料相談はこちらから!/
まとめ
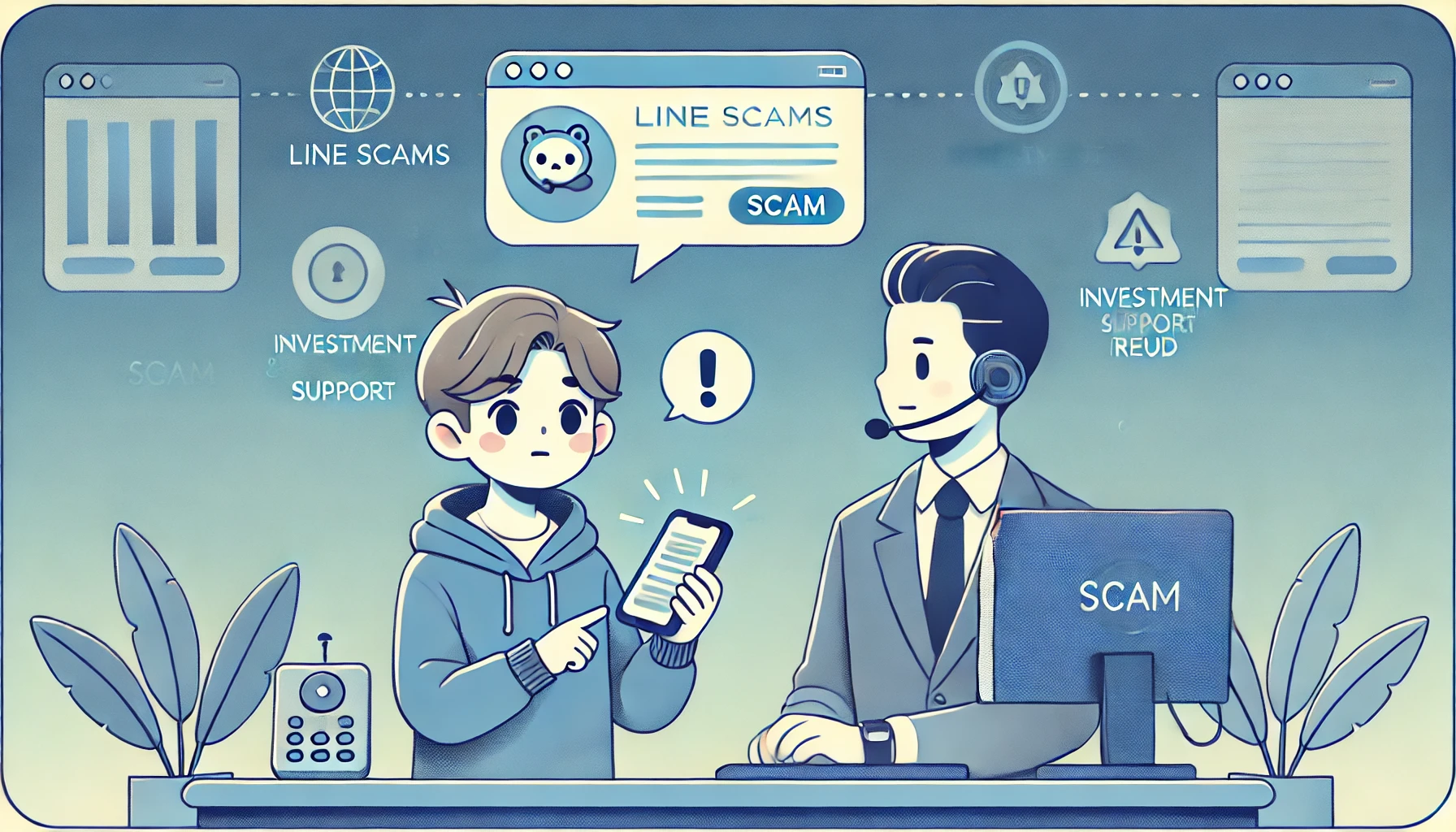
楽に収入を増やしたいという望みは誰もが抱くものですが、「誰でも必ず稼げます」「返金保証つきで安心です」などの甘い言葉には必ず裏があります。
情報商材詐欺に騙されないためには「うまい話はない」と認識したうえで、あやしい業者の見分け方を知っておくことが重要です。
もしお金を騙し取られても、司法書士・弁護士に相談することで返金に成功する可能性があるため、諦める必要はありません。
丹誠司法書士法人では、情報商材詐欺の解決実績が豊富な認定司法書士が、返金に向けて親身にサポートします。
相談料や着手金は無料ですので「騙し取られたお金を取り戻したい」「自分が騙されているか確認したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。