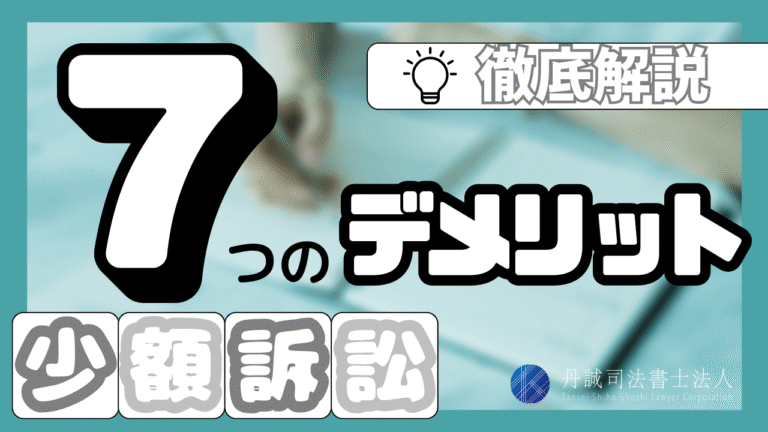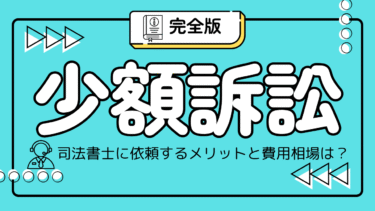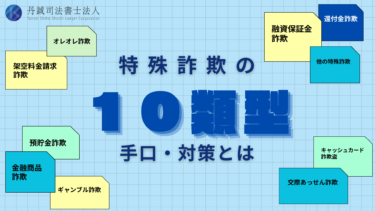「裁判ってなんだか難しそう」「お金も時間もかかりそうで不安」そんなふうに感じている方にこそ知っていただきたいのが、「少額訴訟」という制度です。
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる裁判手続きです。
少額訴訟の特徴は、原則として1回の審理で判決が出る点です。
手続きも比較的シンプルで、時間や費用の負担を抑えながら資金回収を図れます。
一方で、制度特有の制限や注意点もあり、すべての金銭トラブルに適しているわけではありません。
制度の内容をよく知らずに利用してしまうと、少額訴訟のメリットを十分に得られない可能性があります。
本記事では、少額訴訟のメリットやデメリット、少額訴訟に適したケース、注意点などを詳しく解説します。
- 少額訴訟の概要と条件
- 少額訴訟のデメリット7つ
- 少額訴訟のメリット3つ
- 少額訴訟に適したケース
- 弁護士や司法書士に依頼する際のポイント
少額訴訟とは?

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める民事訴訟で利用できる手続きです。
紛争を簡易かつ迅速に解決することを目的として設けられた制度で、少額訴訟と通常の訴訟手続きではいくつか異なる点があります。
少額訴訟の条件
少額訴訟を利用するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 請求金額が60万円以下であること(利息や遅延損害金を除く)
- 金銭の支払いを求める請求であること
- 被告の住所が明確で、原則その管轄の簡易裁判所で行うこと
少額訴訟のデメリット7つ

少額訴訟にはメリットがある一方で、いくつかデメリットも存在します。
きちんと理解した上で、利用するか検討しましょう。
デメリット1|書類作成など準備に手間がかかる
通常訴訟と比べると手続きは簡略化されていますが、それでも訴状の作成や証拠書類の準備が必要です。
少額訴訟の場合は弁護士に相談せず、ひとりで対応するケースも多いため、負担は大きいでしょう。
とくに、事案が複雑な場合は少額訴訟にかなりの時間と手間がかかるかもしれません。
デメリット2|通常控訴に移行することもある
少額訴訟を申し立てても、被告が通常訴訟を希望した場合や、裁判官が通常訴訟で審理すべきと判断した場合は、通常訴訟に切り替わります。
その場合、審理は複数回にわたるため時間や費用もかかってしまいます。
デメリット3|「控訴」はできない
少額訴訟では控訴は認められていませんが、判決に不服がある場合「異議申し立て」が可能です。
異議申し立てがあると訴訟は通常訴訟に切り替わり、同じ簡易裁判所で再審理が行われます。
通常訴訟になると、少額訴訟と比べて手続きが煩雑になり審理の回数も増えます。
時間や費用の負担が大きくなるため注意しましょう。
デメリット4|原則、審理は1回のみ
少額訴訟では、原則として審理は1回限りです。
したがって、限られた時間の中で立証や証拠提出を全て行わなければなりません。
準備不足だと、訴訟を提訴しても主張を十分に伝えられないまま判決が下されるおそれもあります。
デメリット5|提起できる回数に年間上限がある
同じ簡易裁判所で少額訴訟を提訴できるのは、1人または1法人につき年間10件までです。
個人だとあまり影響はないかもしれませんが、頻繁に金銭トラブルを抱える業種(貸金業者など)では回数制限がネックになる可能性があります。
デメリット6|分割払い・遅延損害金カットなど不利な判決が出る可能性もある
通常訴訟では一括払いの判決が基本で、遅延損害金の請求も認められます。
しかし、少額訴訟では裁判官が被告の経済事情を考慮し、分割払いや遅延損害金の免除など柔軟な判決を下すケースも多いです。
少額訴訟は、必ずしも原告に有利な判決が下されるわけではないことを覚えておきましょう。
デメリット7|勝訴しても相手から支払われないケースもある
少額訴訟で勝訴しても、判決に基づいて相手が支払うとは限りません。
相手が支払いに応じない場合は、自分で相手の財産を調べ、差し押さえなどの強制執行を申し立てることができます。
しかし、相手の財産情報がわからないと強制執行は難しいため、せっかく判決を得ても実際に回収できないおそれがあります。
少額訴訟のメリットは?

少額訴訟にはデメリットもある一方、以下のようなメリットもあります。
メリット1|「少額訴訟債権執行」が可能になる
少額訴訟で勝訴して確定判決などを得れば、「少額訴訟債権執行」を利用できます。
少額訴訟債権執行とは、相手方が有する金銭債権を差し押さえる手続きです。
この申し立てが認められると、相手方に対して差し押さえ命令が送達されます。
送達日から原則1週間が経過すれば、勤務先や金融機関などの第三者から債権の取り立てが可能になります。
その後、勤務先や銀行など第三債務者から直接、差し押さえた金額が支払われます。
メリット2|1日で判決に至る
少額訴訟では、基本的に1日で判決に至ります。
迅速に手続きが進むので、金銭トラブルの早期解決を図れます。
メリット3|自分でできるため費用が抑えられる
少額訴訟の手続きは通常訴訟に比べて簡易なので、弁護士などに依頼せず自分で手続きを進めるケースも多いです。
その場合は弁護士費用がかからないので、費用の捻出を最小限に抑えられます。
少額訴訟に適したケースとは?

少額訴訟のメリット・デメリットを踏まえると、主に以下のようなケースで利用するのがおすすめです。
敷金の返還請求をする場合
賃貸契約において、退去時に貸主が敷金を返還してくれない場合、少額訴訟の利用が適しています。
敷金の金額や返還条件は契約書に記載されているケースがほとんどで、争点が明確になりやすいためです。
金銭の貸し借りを知人間で行っている場合
知人間でお金の貸し借りをした場合、返済をはぐらかされてしまうかもしれません。
話し合いで解決できない場合、制度を利用すれば返済を求める意思を正式に伝える手段となります。
借用書がなくても、銀行振込の記録や、貸し借りをした際のメールやチャットなどの履歴も少額訴訟の際に証拠として活用できます。
売上代金などを回収する場合
仕事をしたにもかかわらず報酬が支払われないなどのケースでも、少額訴訟は有効な手段です。
請求書や契約書、納品書などの証拠があれば取引の実態を示せるため、裁判所に主張を認められやすくなります。
少額訴訟の注意点は?

少額訴訟は利用しやすい制度ですが、いくつか注意すべき点もあります。
事前に理解したうえで利用するようにしましょう。
相手の情報が不明な場合、訴訟提起が難しいこともある
少額訴訟を起こすには、相手の氏名や住所などの基本情報が必要です。
送付先などが不明だと訴状が送達できず、訴訟の開始が困難になります。
たとえば、インターネット上で知り合った相手にお金を貸したものの、本名や住所も知らない場合は、訴えること自体が難しいです。
ただし、勤務先がわかっていれば勤務先宛に訴状を送付できる場合もあります。
その場合は訴訟提起が可能か、諦めずに弁護士や司法書士へ相談しましょう。
費用倒れになるリスクもある
少額訴訟は比較的費用がかからず利用しやすい制度です。
しかし、請求額が数万円程度と非常に少額の場合に弁護士や司法書士へ依頼すると、費用倒れになる可能性があります。
ただし、少額訴訟のために書類を揃えるなど手間がかかるのも事実です。
弁護士や司法書士に依頼するかどうかは、請求金額の多寡や手間と時間をどれだけかけられるかを考えたうえで決めるのがよいでしょう。
少額訴訟を弁護士・司法書士に依頼するポイントは?

少額訴訟は比較的簡易な手続きであるため、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で対応する方も少なくありません。
一方で、あえて弁護士や司法書士に依頼する人もいます。
弁護士や司法書士に相談すれば、相談者の状況を踏まえた上で「少額訴訟が適しているか」「他の手続きがより適切か」など、最善の選択肢を提示してくれます。
さらに、訴状の作成や証拠書類の準備といった煩雑な作業を一任できるため、自身の負担を大きく減らせます。
特に「自分で手続きするのは不安」「相手と直接やり取りしたくない」という方は、一度相談してみるとよいでしょう。
以下の記事では、少額訴訟を司法書士に依頼するメリットや費用相場について詳しく解説しています。
少額訴訟の手続きを検討している方は、ぜひご覧ください。
少額訴訟は自力でも行えますが、司法書士に依頼することで手間を大きく軽減でき、勝訴の可能性も高まります。 本記事では、少額訴訟を司法書士に依頼するメリットや費用相場、訴訟を成功させるポイントを解説します。 少額の金銭トラブルを速や[…]
少額訴訟と通常訴訟の違いは?
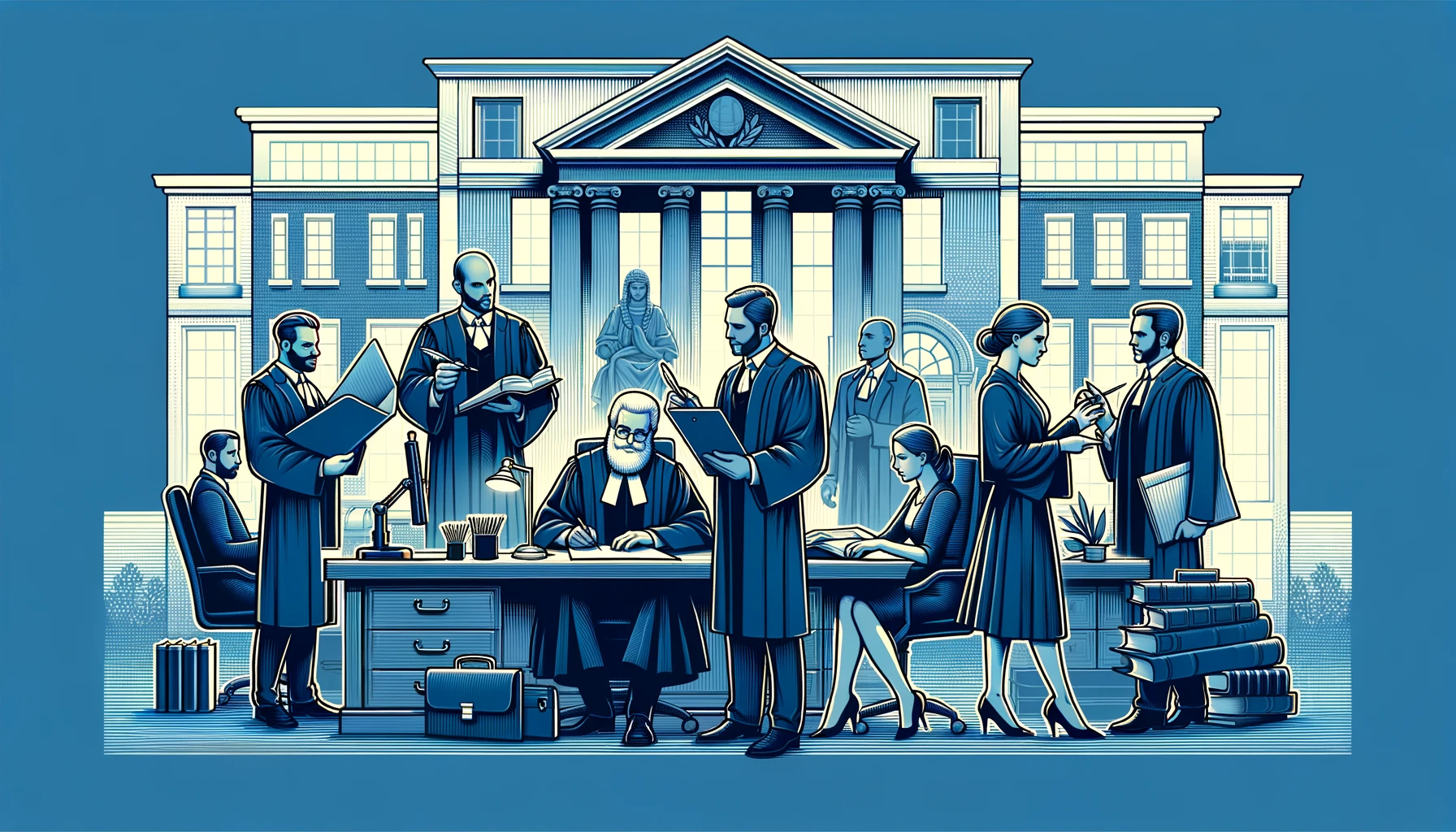
通常訴訟と少額訴訟の主な違いは以下のとおりです。
| 比較項目 | 通常訴訟 | 少額訴訟 |
| 訴訟額・請求内容 | 金額に上限なし 金銭以外も請求可能 |
60万円以下の金銭請求のみ |
| 判決までの期間・控訴の可否 | 数か月〜1年以上かかることもある 控訴可能 |
原則1回の審理で即日判決 控訴は原則不可 |
| 反訴の可否 | 可能 | 不可(反訴したい場合は通常訴訟へ移行する) |
| 送達方法 | 公示送達が可能 | 公示送達は不可(被告本人への直接送達が必要) |
| 裁判にかかる費用 | 比較的高額 | 比較的少額 |
以下で、それぞれ解説します。
訴訟額・請求内容の違い
少額訴訟は60万円以下の金銭請求に限られているため、それ以外の請求(物の返還や契約の履行など)は対象外です。
また、継続的な取引に関する請求も対象外です。
一方で、通常訴訟は請求金額に上限がなく、請求の種類にも制限がありません。
判決までの期間・控訴の可否
少額訴訟は原則として1回の審理で即日判決が出ます。
一方、通常訴訟は審理が複数回に及ぶため判決までに数か月から1年以上かかることもあります。
また、少額訴訟では原則として控訴は認められていません。
一方、通常訴訟では判決に不服がある場合、上級裁判所に控訴して再審理を要求できます。
反訴の可否
反訴とは、被告が原告に対して同じ訴訟の中で訴え返すことをいいます。
双方の請求を一括で審理できるため、効率的で判決の矛盾防止につながるメリットがあります。
通常訴訟では反訴が認められていますが、少額訴訟では認められていません。
もし被告が反訴を主張すれば、通常訴訟に切り替えることになります。
送達方法
通常訴訟では、被告の住所が不明な場合でも公示送達という方法を使って訴訟を進めることができます。
しかし、少額訴訟では公示送達は認められておらず、被告本人に訴状を直接送達する必要があります。
したがって、被告の住所が不明なケースでは、少額訴訟を利用できない点に注意が必要です。
裁判にかかる費用
一般的に、少額訴訟は裁判費用を比較的低く抑えられます。
また、審理も短いため、時間的・精神的なコストも少ないといえます。
一方、通常訴訟は訴額に応じて裁判費用が高くなるうえ審理期間が長期化しやすく、弁護士に依頼する場合の費用も高くなりがちです。
少額訴訟を検討している方は「丹誠司法書士法人」へ相談を!

少額訴訟を利用すれば、早期に資金回収が見込める点が魅力です。
しかし、すべてのケースで少額訴訟が最適とは限りません。
少額訴訟と通常訴訟の仕組みや違いを正しく理解し、自分の状況に合った手続きを選ぶことが大切です。
ただし、自分が置かれた状況ではどちらを選べばよいかわからない方も多いでしょう。
判断や手続きに不安がある場合、まずは弁護士や司法書士に相談しましょう。
丹誠司法書士法人では少額訴訟に関するご相談も受け付けています。
ご相談は無料ですので、「少額訴訟を検討しているけれど判断がつかない」場合も一度お問い合わせください。