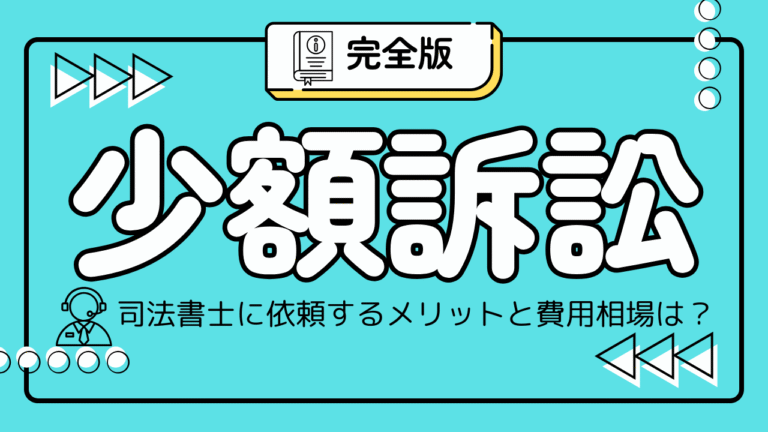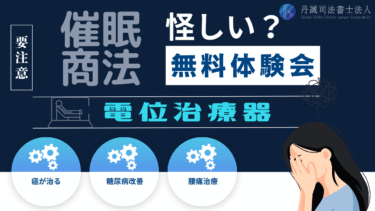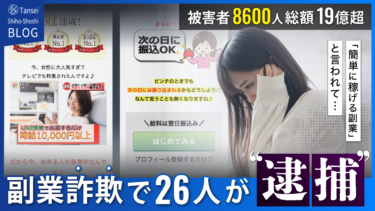少額訴訟は自力でも行えますが、司法書士に依頼することで手間を大きく軽減でき、勝訴の可能性も高まります。
本記事では、少額訴訟を司法書士に依頼するメリットや費用相場、訴訟を成功させるポイントを解説します。
少額の金銭トラブルを速やかに解決したい方は、ぜひご一読ください。
- 少額訴訟を司法書士に依頼するメリット
- 自分で少額訴訟の手続きを行った場合の費用
- 司法書士に少額訴訟を依頼したときの費用相場
- 少額訴訟の流れ
- 少額訴訟を成功させるポイント
少額訴訟を司法書士に依頼するメリット

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを目的とする訴訟です。
原則として1回の口頭弁論によって審理が終了し、その日のうちに判決が言い渡されます。
通常の訴訟に比べて手続きが簡単で、費用も抑えられるのが特徴です。
少額訴訟は個人間の金銭の貸し借りや損害賠償請求、未払い賃金請求、マンションの敷金返還請求など、時間をかけずにトラブルを解決したい場合に向いています。
少額訴訟は一人でも手続きできますが、認定司法書士に依頼することで以下のようなメリットが得られます。
手続きの負担が減る
少額訴訟は通常訴訟に比べて容易に裁判を起こせるものの、訴状の作成や答弁書の受け取りなど、さまざまな手続きが必要です。
司法書士に依頼すれば書類の作成から申し立てや口頭弁論のサポートまで一任できるため、訴訟にかかる手間や時間を大幅に削減できます。
自分で行うより裁判を有利に進めやすくなる
司法書士に少額訴訟を依頼することで、主張や証拠の構成が適切になり、裁判を有利に進めやすくなるのもメリットのひとつです。
少額訴訟は原告が勝訴する割合が高いとされていますが、証拠が不十分だったり弁論の際に主張の仕方を間違えたりすると、不利になってしまうことがあります。
被告に弁護士や司法書士がついている場合、法的知識に基づいた反論によって自分の主張が覆される可能性もあるでしょう。
少額訴訟の実績が豊富な司法書士を代理人に立てることで、訴訟全体の準備や進行がスムーズになり、より有利に手続きを進められます。
弁護士に依頼するより費用を抑えられる可能性がある
少額訴訟の場合、弁護士よりも司法書士に依頼したほうが費用を抑えられる可能性があります。
費用負担を軽減するためには、無料相談を実施している司法書士事務所を選ぶのもひとつの方法です。
また、事務所によって料金体系が異なるため、複数の事務所から見積もりをとって比較検討するのもおすすめです。
複雑な訴訟や証拠が不十分な場合など、そもそも少額訴訟が適さないケースもあります。
「少額訴訟がベストな選択肢なのか」も含め、まずは無料相談を実施している司法書士事務所にアドバイスを求めてみましょう
自分で少額訴訟の手続きを行った場合の費用

自分で少額訴訟の手続きを行う場合の費用目安は下記のとおりです。
| 費用内訳 | 費用相場 |
| 訴訟手数料 (収入印紙代) |
1,000円~6,000円 (訴額によって異なる) |
| 予納郵券代 (訴状の送達や判決の送付などに使用) |
3,000~6,000円程度 (裁判所や当事者の人数によって異なる) |
| その他 | 交通費、証拠書類のコピー代、証人の日当など |
証人の手配などを行わなければ、多くの場合、費用は合計1万円程度に収まるでしょう。
司法書士に少額訴訟を依頼したときの費用相場

司法書士に少額訴訟を依頼した場合の費用は、依頼内容や事務所ごとの料金体系によって異なります。
たとえば「訴状の作成のみ任せたい」「裁判所での手続きを代理してほしい」など、業務の範囲によっても金額が変動します。
おおよその費用目安は下記のとおりです。
| 費用内訳 | 費用相場 |
| 相談料 | 30~60分で5,000円程度 |
| 着手金 | 3万円~6万円程度 |
| 訴訟手数料 (収入印紙代) |
1,000円〜6,000円 (訴額によって異なる) |
| 予納郵券代 | 3,000~6,000円程度 (裁判所や当事者の人数によって異なる) |
| 訴状作成料 | 30,000円程度 (訴状の作成のみ依頼した場合) |
| 少額訴訟代理費 | 30,000円程度 (訴訟手続きを一任した場合) |
| 簡易裁判所訴訟代理費 | 50,000円程度 (訴訟代理人を依頼した場合) |
| 日当 | ・期日日当:8,000円~10,000円程度 (裁判所への同行費用など) |
| 出張・現地調査費 | 実費 (交通費など、必要に応じて発生する場合あり) |
| 成功報酬 |
|
司法書士事務所によって料金体系が異なるため、相談料や着手金が無料のケースもあります。
ただし、少額訴訟は請求額そのものが少額なため、回収できた金額よりも依頼費用が上回ってしまう可能性も考えられます。
費用倒れになる心配がないか、相談時に司法書士に確認しておきましょう。
少額訴訟の流れ

本人が裁判所での手続きを行い、訴状の作成のみ司法書士に依頼することも可能です。
少額訴訟の流れを知っておけばスムーズに手続きしやすくなります。
ここでは、少額訴訟の流れを5つにわけて紹介します。
1.訴状の提出
まずは訴状を作成し、被告の住所地を管轄する簡易裁判所に提出します。
提出方法は裁判所の窓口への持参または郵送が可能です。このとき、契約書や借用書、請求書などの証拠も提出しましょう。
2.裁判期日の通知
簡易裁判所が訴状を受理すると、原告・被告に対して裁判期日(裁判所に出頭する口頭弁論期日の日時)が記載された呼び出し状が送付されます。
原告には手続き説明書、被告には訴状も同封されます。
3.事前聴取・答弁書の受け取り
少額訴訟は1回の審理で結審するため、裁判を円滑に進めるべく事実関係の確認や追加の証拠提出が求められることがあります。また、裁判期日前には、被告の言い分がまとめられた答弁書が届きます。
内容をよく確認し、裁判期日に有効な立証ができるよう準備しておきましょう。
4.裁判期日
裁判期日には、訴状の控えや訴状に押印した印鑑、証拠書類の原本を忘れずに持参しましょう。
当日は原告・被告・裁判官・書記官・司法委員がテーブルを囲み、審理が進行します。
所要時間は約30分〜2時間程度です。
5.和解・判決
原告・被告が和解すると、支払い金額や支払い方法、支払い期限などが記載された和解調書が作成され、裁判が終了します。
和解に至らなかった場合は裁判官が双方の主張と証拠を確認し、判決を言い渡します。
判決に不服があっても控訴はできませんが、言い渡しから2週間以内であれば原告・被告ともに異議申し立てが可能です。
異議申し立てが認められた場合は通常訴訟に移行し、同じ簡易裁判所で再度審理が行われます。
また、少額訴訟で原告が勝訴しても、被告が判決や和解内容どおりの支払いをしない場合は強制執行に踏み切ることも可能です。
この場合は被告の財産を特定し、簡易裁判所に差し押さえの申し立てを行いましょう。
少額訴訟を成功させるポイント

少額訴訟は原則として1回の審理で終わり、あとから証拠を追加することができません。
裁判では証拠が重視されるため、可能な限り多くの証拠を集めておくことが重要です。
契約書や請求書、領収書、録音した通話記録、メールなど、証拠が明確であればあるほど説得力が増し、裁判を有利に進められます。
また、訴訟前に事実関係を整理し、時系列にまとめた書類を準備しておくのもおすすめです。
これにより、「どのように主張を展開するか」「被告の反論に対してどのように応じるか」といった対策を講じやすくなり、勝訴の可能性が高まります。
まとめ
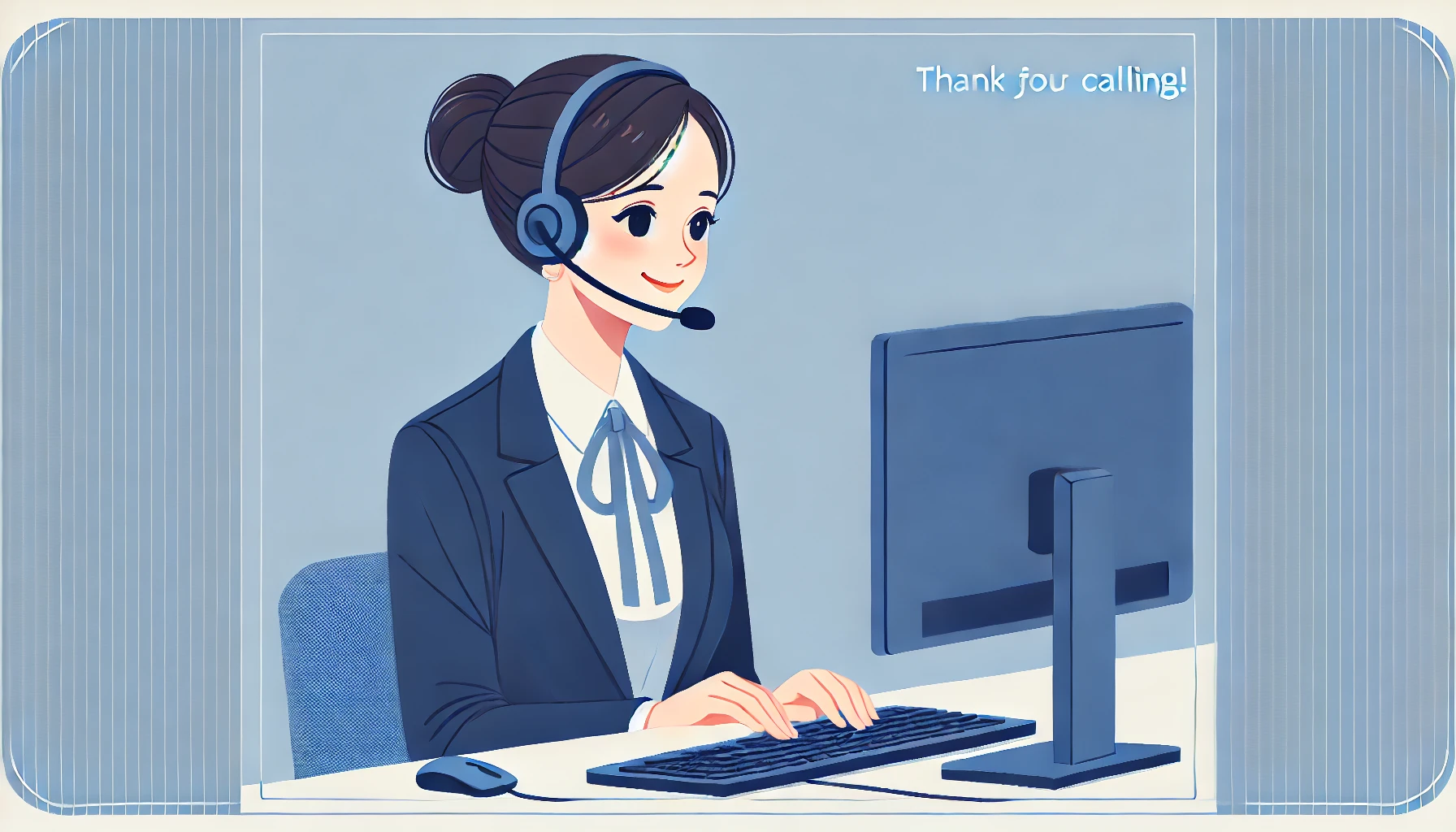
司法書士に少額訴訟を依頼するメリットは下記のとおりです。
- 手続きの負担が減る
- 自分で行うより勝訴の可能性が高まる
- 弁護士に依頼するより費用を抑えられる可能性がある
少額訴訟の手続きにかかる手間や時間を節約したい方、勝訴の可能性を高めたい方は司法書士への依頼を検討してみましょう。
費用倒れにならないよう、相談時に「トータルでいくらかかるのか」をよく確認しておくことが大切です。
丹誠司法書士法人では、経験豊富な認定司法書士による少額訴訟のサポートを行っています。
「少額訴訟を依頼すべきか迷っている」「少額訴訟も含め、ベストな解決方法を教えてほしい」という方も、お気軽にお問い合わせください。