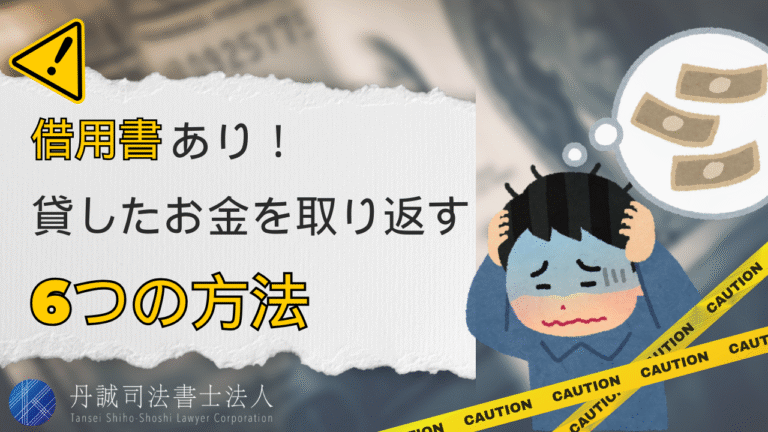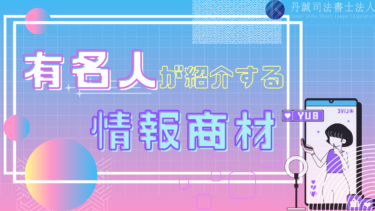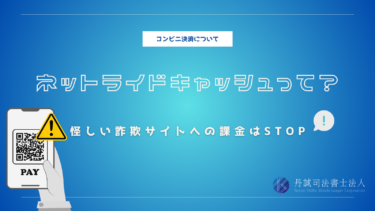「借用書があるのに、貸したお金を返してもらえない」
「一日も早くお金を取り返す方法は?」
友人や親戚、職場の同僚などにお金を貸したものの、返済期限を過ぎてもお金を返してくれずに困っていませんか。借用書があればお金を取り戻せる可能性が上がりますが、適切な回収方法は状況によって異なります。
本記事では、借用書がある場合に貸したお金を取り返す方法や、回収率を上げるポイントを解説します。
- 借用書の有効性
- 貸したお金を取り返す方法6つ
- 貸したお金の回収率を上げるポイント
- 弁護士・司法書士に相談するメリット
- 弁護士・司法書士に借金の回収を依頼した場合の費用相場
\早めの相談が最重要!/
借用書があればお金を取り返せる可能性が高まる

借用書とは、金銭・物品の貸し借りの事実や返済の義務を明確にする書面です。
法的には、口約束であっても債務者(お金を借りた人)に返済義務が発生するため、借用書がなくても債権者(お金を貸した人)には返済を要求する権利があります。
しかし、借用書がなければ「お金は受け取っていない」「もらったものだと思っている」などと借金を踏み倒されるケースもあります。
この場合、銀行の振込履歴やメールのやり取りなどで、お金の貸し借りを証明しなければなりません。
借用書があれば債務者が言い逃れできなくなり、裁判になった際も「お金の貸し借りがあった」という事実を明確に証明できます。
借用書に債務者の署名や捺印があればより強力な証拠になり、回収率が上がります。
司法書士に依頼することで、より確実にお金を取り返せるかもしれません。検討している方は、以下よりご相談ください。
\心当たりがある人はすぐ相談!/
貸したお金を取り返す方法6つ

貸したお金を取り返す方法は、以下の6つです。
- メール・電話・訪問などによる直接催促
- 内容証明郵便の送付
- 民事調停
- 支払督促
- 少額訴訟(元本が60万円以下の場合)
- 通常訴訟(元本が60万円を超える場合)
それぞれくわしく解説します。
1.メール・電話・訪問などによる直接催促
連絡が取れる状態であれば、まずはメールやLINEで催促のメッセージを送ってみましょう。「早くお金を返してよ」などと直接的に伝えるのではなく「いつ頃返してもらえるかな?」「目途はつきそう?」などとやんわり尋ねることで、相手にプレッシャーを与えずに状況確認できます。
このとき、「もう少し待ってほしい」などと返済の意思を示す返信があった場合、相手が借金を認めた証拠になる可能性があります。メッセージをスクリーンショットで保存しておきましょう。
また、電話や手紙での催促も有効です。電話なら相手の反応を即座に確認でき、手紙なら感情的にならず冷静に催促できます。
メッセージや電話、手紙に反応がなければ相手の自宅を直接訪問するのもひとつの方法ですが、催促の際に高圧的な態度をとると脅迫と見なされるリスクがあるため注意してください。夜間や早朝の訪問、執拗な催促は避け、落ち着いて話し合うことが大切です。
2.内容証明郵便の送付
相手と連絡が取れないとき、催促してもお金を返してくれないときは内容証明郵便でお金の返済を求めるのも有効です。
内容証明郵便とは、いつ・誰から誰に・どのような内容の文書を送付したかを日本郵便株式会社が証明してくれるサービスです。配達証明のオプションをつければ、相手が確実に受け取ったという事実も証明でき、のちに裁判になった際も重要な証拠になり得ます。
なお、内容証明郵便そのものに返済を強制する法的な効力はありませんが、相手に心理的なプレッシャーを与えることで支払いに応じてもらいやすくなります。
また、内容証明郵便を送ることで時効の成立を6か月延長できるのもメリットのひとつです。
3.民事調停
内容証明郵便を送付しても相手が返済に応じない場合、法的手続きを検討しましょう。
民事調停とは、裁判官・調停委員(裁判所が任命した仲介人)が間に入り、当事者間の話し合いによって問題解決を目指す手続きです。
民事調停であれば弁護士に依頼しなくても本人が手続きを進められるため、訴訟に比べて申立て費用を安く抑えられます。
訴訟のように裁判官が判断を下すのではなく、債務者・債権者の双方が主張を伝え合ったうえで合意を目指すため、穏便に解決しやすいというメリットもあります。
ただし、民事調停はあくまでも話し合いで問題を解決するための手続きであり、必ずしも調停が成立するとは限りません。
双方の意見が折り合わない、相手が出席しない、などの理由で調停が不成立となる場合もあります。
4.支払督促
支払督促(しはらいとくそく)とは、債権者が簡易裁判所に申し立てを行い、書記官から債務者に対してお金を返すよう命じてもらう手続きです。
請求金額に関係なく申し立てができ、訴訟よりも費用負担を軽減できます。また、支払督促は簡単な書面審査のみで支払督促を発付してもらえるため、裁判所に出向く必要もありません。
支払督促を送っても債務者が異議を申し立てずお金も支払わない場合、債権者は裁判所に「仮執行宣言」を発付してもらうことで、強制執行が可能になります。
ただし、債務者が異議を申し立てた場合は訴訟手続きに移行します。
5.少額訴訟(元本が60万円以下の場合)
少額訴訟とは、元本60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルにおいて迅速かつ低コストでの解決を目指せる制度です。
少額訴訟を起こす場合は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に訴状を提出します。
原則として1回の審理で即日判決が下されるため、早期解決を目指せるのがメリットです。通常の訴訟に比べて申立手数料が安く、経済的な負担も抑えられます。
ただし、被告が少額訴訟に異議を申し立てると通常訴訟に移行し、問題が長期化する可能性があります。
6.通常訴訟(元本が60万円を超える場合)
これまで紹介した方法でお金を返してもらえない場合や、元本が60万円を超えている場合は通常訴訟を検討しましょう。
また、少額訴訟利用回数の制限(10回)を超えている、相手の住所がわからないなど、少額訴訟を適用できない場合も通常訴訟が選択肢となります。
元本が140万円以下の場合は簡易裁判所、元本が140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出しましょう。
ただし、法律知識のない方が自力で通常訴訟を起こすのは非常に難しいため、弁護士に依頼するのが一般的です。簡易裁判所における140万円以下の民事訴訟においては、認定司法書士も代理人として手続きを行えます。
訴訟においては証拠が勝敗を分けるケースが多いため、弁護士・司法書士のアドバイスの下で、証拠をしっかり収集・整理しておきましょう。
なお、裁判に勝訴し判決が確定しても被告がお金の返済に応じない場合は、強制執行の申し立てが可能です。
ただし強制執行の申し立てをする際は債権者が債務者の財産(銀行口座、不動産、勤務先など)を特定しなければなりません。
\心当たりがある人はすぐ相談!/
貸したお金の回収率を上げるポイント

借用書がある場合、以下のポイントを押さえればさらに回収率がアップします。
借用書の有効性を確認する
借用書はお金の貸し借りを証明する契約書として法的効力がありますが、場合によっては無効になってしまう可能性もあります。まずは借用書の有効性を確認しておきましょう。
<無効になる可能性がある借用書の例>
- 制限行為能力者(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人)との契約である
- 公序良俗違反の契約(犯罪目的での貸し借り・返済のために違法行為を要求)である
- 利息制限法の上限金利を超える利息や遅延損害金の取り決めがある
- 記載された内容に錯誤(双方で金額の認識が異なるなど)がある
なお、借用書に不備があっても、当事者間の同意があれば借用書を作り直すことができます。借用書の作成や修正に不安がある場合は、弁護士や司法書士に依頼するのが確実です。
そのほか、銀行の振込明細書やメッセージのやり取り、電話の録音など、借用書以外の証拠を集めるのも有効です。
時効が成立する前に行動する
お金の貸し借りにも時効があり、債務者に対して長期間返済を求めなかった場合、債権者はお金を請求する権利を失ってしまいます。
借金返済を請求する権利(貸金債権)の時効は、以下のいずれか早いタイミングで成立します。
- 権利を行使できると知ったときから5年
- 権利を行使できるときから10年
借用書があれば返済期限が定められていることが多いため、この場合は返済期限の翌日から5年が経過すると時効が成立します。
また、長期間経過すると債務者の経済状態が悪化し、債務整理手続きをとられてしまうこともあります。貸したお金を取り返すためには、時効の期間にかかわらず早めに行動しましょう。
相手を脅さない
債権者には、債務者にお金の返済を求める正当な権利があります。しかし、相手を脅したり怒鳴ったりすると脅迫罪が成立する可能性があるため注意が必要です。また、脅迫によってお金を取り返した場合は恐喝罪に問われる可能性もあります。
このようなリスクを回避するためには当事者間で解決しようとせず、第三者に相談することをおすすめします。
\もしかして…と思ったら即相談!/
返済が難航している場合は弁護士・司法書士への相談が有効

返済が難航している場合や、債務者が返済の意思を示さない場合は、弁護士や司法書士への相談が有効です。
返済が見込めない状況でも、弁護士・司法書士に相談することでお金を取り返せる可能性が上がります。
たとえば弁護士・司法書士の名義で内容証明郵便を送ることで、債務者に強いプレッシャーを与えられ、すんなり返済されるケースもあります。
裁判を起こす場合も、弁護士や認定司法書士に依頼することで複雑な手続きを一任でき、時間的・精神的な負担が大きく軽減します(認定司法書士は、簡易裁判所における140万円以下の民事裁判のみ代理人として手続きが可能)。
また、相手に財産がなければお金を取り返すのが難しくなりますが、弁護士・司法書士に相談すれば費用倒れになる可能性も含めてアドバイスを受けられます。
無料相談に対応している弁護士事務所・司法書士事務所もあるため、ぜひ活用してください。
なお、丹誠司法書士法人でも無料相談を実施しています。お気軽にご相談ください。
弁護士・司法書士に借金の回収を依頼した場合の費用相場

弁護士や司法書士に借金の回収を依頼する場合の費用は事務所によって異なります。
また、事務所によって料金体系も異なり、相談料・着手金が無料の事務所や、依頼内容や債権額によって金額設定している事務所もあります。具体的な費用は、相談時に見積もりを出してもらうのが確実です。
\無料相談はこちらから!/
まとめ
借用書ありで貸したお金を取り返す場合、まずはメールや電話、自宅訪問などによる催促が第一歩です。債務者が任意の請求に応じない場合は内容証明郵便を送付するほか、民事調停や支払督促、少額訴訟、通常訴訟といった法的手段を検討しましょう。
どのような方法で催促すべきかは相手との関係性や状況、借金の金額などによって異なりますが、弁護士や司法書士に依頼することで適切な方法を判断してもらえます。
丹誠司法書士法人では、認定司法書士が相談者様の状況に応じた的確なアドバイス・サポートを行っています。
相談料や着手金は無料ですので、まずは一度お話をお聞かせください。
\返金確認こちらから!/