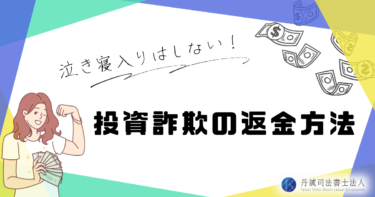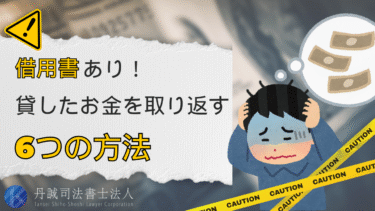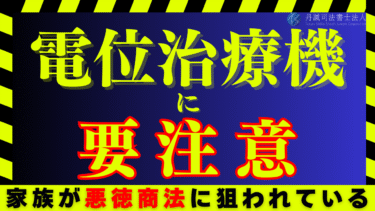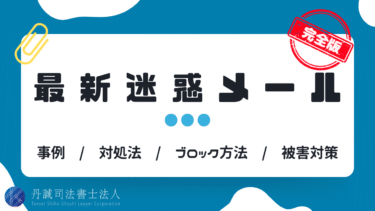「上場すれば何倍にもなる」「今だけ関係者限定で購入できる」といった言葉に心を動かされた経験はありませんか?
金融庁や消費者庁によると、未公開株をめぐる詐欺の被害は高齢者を中心に現在も後を絶たず、被害総額が数億円規模にのぼるケースも珍しくありません。
代金を支払ったのに株券が届かない、連絡が取れないといった被害が報告されています。
本記事では、未公開株詐欺の実態や典型的な手口、実際に起きた事例をもとに、被害にあわないためのポイントや、被害にあってしまった場合の相談先について詳しく解説します。
- 未公開株詐欺の仕組みと代表的な手口
- 実際に起きた被害の事例
- 被害を防ぐための対策と万一の相談先
以下の記事では、投資詐欺で泣き寝入りしないために知っておきたい返金方法をご紹介します。
「返金されないのでは?」と不安を感じている人は、ぜひ一度ご覧ください。
投資詐欺にあったと気がついたときに「返金されないのでは?」なんて不安を感じている人はいませんか? この記事では、投資詐欺で泣き寝入りしないために知っておきたい返金率や返金事例をご紹介します。 [afTag id=5415] ✓[…]
未公開株詐欺とは

未公開株詐欺とは、「近く上場予定の有望企業の株がある」と偽り、一般には流通していない株式を購入させることによって金銭を騙し取る手口を指します。
未公開株は、証券取引所に上場していない企業の株式です。
株式市場を通さず、売主と買主が直接交渉して譲渡されます。
法律上は当事者間の合意があれば売買は可能ですが、市場価格が存在しないため、価格の妥当性を判断する材料が極めて乏しいのが実情です。
未公開株詐欺では「上場すれば何倍にも値上がりする」「毎年高配当が見込める」など、投資家心理を巧みに突く甘い言葉で勧誘してきます。
しかし、実際にはその企業に上場の見込みは一切なく、購入後に連絡が取れなくなるといった被害が後を絶ちません。
未公開株は証券取引所で売買されていないため、株価の動きを確認する術がなく、「株価が急騰している」と言われても、その真偽を個人が独自に確かめることは困難です。
未公開株詐欺の現状
日本証券業協会の「令和2年度「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンター通報状況」の報告によると、4月には未公開株詐欺が全体の22%を占めており、5月にはその割合が36%と大きく上昇しました。
その後もほぼ横ばいで推移しており、未公開株詐欺が断続的かつ継続的に発生しています。
また、警察庁の資料によると、2023年の未公開株詐欺による検挙事件は2件、検挙人員は7人と、件数・人数としては決して多くはありません。
しかし、被害者は15,098人にのぼり、被害総額は107億円に達しています。
未公開株詐欺の手口

未公開株詐欺には、いくつかの典型的なパターンがあります。
いずれも巧妙な演出によって、あたかも未公開株の購入が可能であると思わせたり、確実に価値が上がると信じ込ませたりするものです。
未公開株詐欺の代表的な手口を紹介します。
上場予定を偽る手口
「この企業は上場が決まっている」「上場すれば2倍以上の価値になる」などと語り、実際には存在しない上場計画を根拠に未公開株の購入を迫る手口です。
あたかも内部情報のように話すことで信頼感を与え、さらに「関係者しか買えない」などと特別枠を演出して投資家心理を揺さぶります。
株券が渡されない手口
未公開株を購入したにもかかわらず、いつまでも株券が手元に届かないという手口です。
「現在名義変更中」「信託銀行で保管中」などと理由をつけて株券の引き渡しを遅らせ、その代わりに「預かり証」や「購入証明書」といった法的効力のない書面だけを渡されるのが典型的なパターンです。
いくら催促しても「少し待ってほしい」と言われ続け、最終的には連絡が取れなくなります。
架空の会社を使う手口
実在しない企業名をでっち上げ、投資話を持ちかけるのもよくある手口です。
見た目は本物のような名刺やパンフレット、企業サイトを用意し、「資本金○億円」「世界展開中」などもっともらしい情報で信用させようとします。
しかし、所在地や電話番号はすべて虚偽で、登記情報などの裏付けが取れない場合がほとんどです。
金融庁等を装う手口
「この投資は金融庁の認可を受けています」「当方は金融庁から委託されて動いています」など、あたかも公的機関の後ろ盾があるかのように装って安心感を与える手口です。
「投資アドバイザー」や「資産管理士」などの肩書を語るほか、実在しない団体名や人物を名乗るケースも見られます。
未公開株の「買い取り」を装った詐欺の手口
すでに未公開株を購入してしまった人をターゲットに、「保有されている未公開株を高額で買い取ります」と電話をかけてくる二次被害型の詐欺もあります。
有名な証券会社に似た名前を名乗ったり、金融業者風の名刺を使ったりします。
買い取りの条件として、私募債・信託券・権利証など別の商品の購入を求められ、支払いが済んだ後には音信不通になるのが典型パターンです。
未公開株の詐欺的手法の事例

未公開株詐欺は、巧妙な話術と限定性・将来性を装った演出によって投資家の判断力を奪い、金銭をだまし取る手口で被害が引き起こされます。
ここでは、実際に金融庁が公表している事例をもとに、よくある未公開株の詐欺的手法とその特徴を紹介します。
上場間近と偽られた事例
業者から「上場間近で大きな利益が見込める」と勧誘され、未公開株を購入しました。
代金の支払い後、業者からは株券の代わりに「預り証」が渡されましたが、肝心の株券は一向に届きません。
不審に感じて発行会社に確認したところ、「上場の予定は一切ない」と告げられました。
「上場間近」という言葉で投資家心理を煽り、株式の実体すら伴わない状態で代金を集めるという典型的な手口です。
株券の代わりとして「預り証」という法的効力のない書類を渡すことで、ターゲットを信じさせます。
買付代金を渡した後に業者と連絡が取れなくなった事例
業者から未公開株の購入を持ちかけられ、買付代金を支払いました。
しかし、その後は一切連絡がありません。
不安に思って業者に電話をかけても、すでに繋がらない状態になっていました。
契約書や株券の受け取り前に代金を支払うと、悪徳業者と連絡が取れなくなります。
業者は存在しない会社名を名乗っていることも多く、新たな連絡先をインターネット検索しても見つけることはできません。
上場を装った虚偽説明と名義書換拒否の事例
業者から「今年の秋に上場する予定がある」と勧誘され、未公開株を購入しました。購入後、株券の名義書換えを求めたところ、「少し待ってほしい」と言われ続け、手続きは一向に進みません。
不審に感じて発行会社に確認したところ、「上場の予定はなく、当社の株式には譲渡制限があるため名義書換えはできない」と回答を受けました。
上場予定というもっともらしい嘘と、制度の理解の甘さを突いた手口です。
未公開株は、第三者である業者から勧誘を受けて購入はできません。
しかし、知識不足により、法律上問題がないと思い違いをしてしまいます。
未公開株詐欺を防ぐ方法

未公開株詐欺は、専門知識の不足につけ込む悪質なものです。
いくつかの基本的な確認と心構えを持っておくことで、被害を防ぐことができます。
ここでは、未公開株詐欺にあわないための方法について詳しく紹介します。
勧誘人の所属団体・企業を確認する
未公開株を販売できるのは、その株を発行している企業自身か、金融庁に登録された正規の証券会社に限られています。
また、現在では正規の証券会社でも未公開株の勧誘は行えません。
過去には「グリーンシート銘柄」と呼ばれる一部の未公開株に限り勧誘が認められていましたが、2018年に廃止されています。
「グリーンシートだから安心」などという説明はすでに通用しないため、古い情報を信じさせようとする業者には要注意です。
自ら未公開株の購入を検討する場合でも、取引相手が金融庁に登録されている業者かどうかを必ず確認しましょう。
発行会社でも不審に思った時点で取引を避ける
「発行会社が直接勧誘してきたから安心」というのは大きな誤解です。
過去には、実在する企業を装って虚偽の勧誘を行うケースや、実在の発行会社が詐欺グループと共謀していたケースも存在します。
どれだけ企業の資料や説明が整っていても、「上場予定」「関係者限定」など、都合のいい話ばかりが並んでいる場合は特に注意が必要です。
一瞬でも不信感を抱いたら、取引を中止しましょう。
未公開株の性質や換金ルールを理解しておく
未公開株は、株式市場で自由に売買できない性質の株です。
上場していない以上、市場価格が存在せず、換金したくても買い手が見つからなければ現金化は不可能です。
また、たとえ上場が決定しているとしても、株価が上がる保証は一切ありません。
上場直後に値を下げるケースもあります。
「必ず儲かる」「値上がり間違いなし」といったセールストークを信じないようにしましょう。
未公開株詐欺にあったときの相談先

未公開株詐欺の被害にあった場合、できるだけ早く専門の窓口に相談することが重要です。
時間が経つほどに対応が難しくなります。
ここでは、主な相談先とそれぞれの役割について紹介します。
警察
警察相談専用窓口「#9110」に連絡すれば、詐欺の手口に関する情報や、今後の対応について助言を受けることができます。
警察が対応できるのは、情報提供や問題解決に向けたアドバイスです。
悪徳業者に支払ったお金を取り戻してくれるわけでは無いため、その点も踏まえて相談しましょう。
とはいえ、他の被害者との関連性が発見され、詐欺グループ全体が摘発されるケースもあるため、情報提供の意味でも相談は有効です。
消費生活センター
消費者ホットライン「188番」は、消費者トラブル全般を扱う公的な相談窓口です。
未公開株詐欺についても相談を受け付けており、具体的な対処法や手続きに関するアドバイスを無料で受けることができます。
ただし、返金や損害賠償の交渉は原則として被害者本人が行う必要があります。
電話相談のあと、必要に応じて地域の消費生活センターに紹介されます。
司法書士・弁護士
被害金の返還を目指したい場合は、司法書士や弁護士に相談するのが有効です。
代理人として、返金請求や交渉、訴訟などを代行できます。
直接のやり取りに不安がある場合でも、本人の代わりに対応してくれることで精神的な負担が大幅に軽減されます。
初回相談が無料の事務所もあるため、早い段階で一度話を聞いてもらうとよいでしょう。
まとめ

未公開株詐欺では、「上場予定」「高配当」「関係者限定」といった言葉を使い、投資家の期待や焦りにつけ込みます。
本記事では、未公開株詐欺の典型的な手口や実際の事例、被害を防ぐためのチェックポイントを紹介しました。
少しでも「おかしい」と感じた場合は、自分だけで判断せず、専門の相談窓口に早めに相談することが大切です。
丹誠司法書士法人では、未公開株詐欺に関するご相談を無料で受け付けています。
「こんなことで相談していいの?」「もう遅いかもしれない」と迷っている方も、まずは一度ご相談ください。