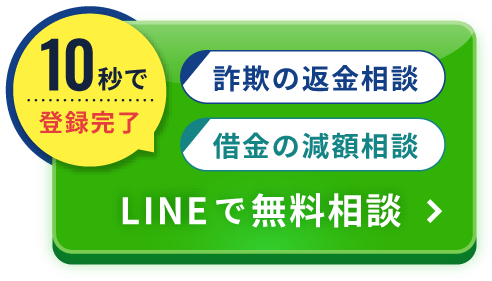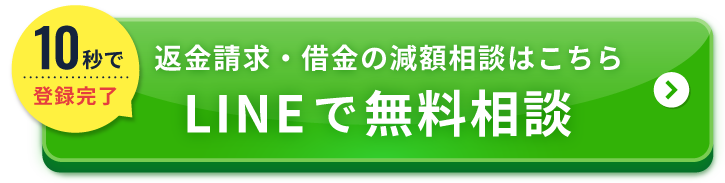遺言書作成
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項(遺言事項)は、法律で決まっています。
相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合にはもちろん遺言書の作成が効果的ですが、それ以外にも、以下のようなケースに当てはまる方は遺言の作成を検討しておくのがお勧めです。
- 子どもがいない
- 相続人が1人もいない
- 相続人の数が多い
- 内縁の妻(または夫)がいる
- 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
- 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
- 家業を継ぐ子どもがいる
- 遺産のほとんどが不動産だ
- 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない
- 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
- 隠し子がいる
- 遺産を社会や福祉のために役立てたい
- 相続に自分の意志を反映したい
- 特定の人だけに財産を譲りたい
- 推定相続人以外に相続させたい
- 財産を予め同居している子の名義にしておきたい
遺言書の作成方法
遺言書のほとんどは、自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれかの方式で作成されています。
それぞれ法律によって厳格に書き方が定められていて、書式に不備があった場合は無効になってしまうことがあります。きちんとした遺言書を作成したいのであれば、1度専門家にご相談することをお勧めします。
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。用紙や筆記具に制限はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。また、録音や映像も無効です。
手軽に作成可能で費用もかからず、また誰にも知られずに作成することが可能です。
反面、内容が不明確になりがちで後日トラブルになることも少なくありません。形式の不備によって無効になりやすいというデメリットもあります。また、遺言書を自身で保管するため、亡くなったあとに紛失や偽造・変造、隠匿のリスクもあります。
さらに、相続の開始後には家庭裁判所での検認手続きも必要なため、遺言の執行までに時間がかかってしまうことがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管します。言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
口述の際には、2名以上の証人の立会いが必要です。相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、公証人の配偶者・4親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
作成に費用がかかってしまいますが、公証人が内容を確認しますので、作成方法について無効になるおそれはありません。遺言書の原本は公証役場に保管され、生前は作成者本人以外が内容を閲覧することはできません。また、家庭裁判所での検認手続きが不要のため、死後すぐに遺言の内容を実行できます。安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
遺言の執行手順
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取り消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。その行為をしてくれるのが遺言執行者です。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任していないときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任の請求をすることができます。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、司法書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は以下のような手順で遺言の執行に取り掛かります。
1.遺言者の財産目録の作成
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2.相続人の相続割合の指定、遺産分配の実行
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
3.相続財産の不法占有者に対して明け渡し・移転の請求
4.遺贈受遺者への遺産引き渡し
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
5.認知の届出
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6.相続人廃除、廃除取り消しの申し立て
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
遺言執行など複雑な手続きの処理を任せるなら、やはり専門知識をもった司法書士にその職務を依頼することが望ましいです。
司法書士へは自筆証書遺言を作成するときのアドバイスや、公正証書遺言の作成支援を依頼することもできます。
また、相続開始まで遺言書の保管を任せることもできます。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。
あらかじめ司法書士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。当事務所では、お客様の状況に合わせて迅速な対応をいたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。